こんにちは、Yatzです!
CMの「ビズリーーーーッチ!」でお馴染みのビズリーチをテーマにしたお話です。

† 出典元:ビズリーチ公式YOUTUBEチャンネル
このケースはシンプルに参考になりました。
転職のお世話になる側としては、エージェントの一つが増えただけという認識でいましたが、ケースを読んでからリクルートの隙間に入っていく秀逸さには、ただただ感心したという感じです。
ビズリーチが、人材業界における革新的なビジネスモデルの変化と価値創出につながったのかをっ自分自身の備忘録として振返ります。
ケースの要約
ビズリーチは2009年に創業され、求職者課金型という当時の日本では前例のない転職サイト「ビズリーチ」をスタートさせた。設立当初はたった6人でのスタートだったが、2018年には130名の大量採用を実施するまでに成長。転職サイトとして、企業・ヘッドハンター・求職者の三者が情報交換できるオープンなプラットフォームを構築した。
創業者の南壮一郎氏は、楽天イーグルスでの実務経験やモルガン・スタンレーでの投資業務のキャリアを持ち、転職活動で感じた「27人のヘッドハンターが全く違う仕事を勧めてくる」という違和感を出発点に、「情報の非対称性」にメスを入れた。
従来の日本の人材業界では、求人広告企業や人材紹介会社がクローズドな情報を保有し、求職者は自分に本当に合った求人に出会う機会が限られていた。さらに、企業側も紹介会社に登録されている限られた求職者としか出会えず、採用のミスマッチが頻発していた。こうした状況を打破すべく、南氏はアメリカのラダーズ社をベンチマークとし、真剣な求職者が自らお金を支払うことでよりよい求人と出会える場を日本に作ろうと考えた。
この課金型モデルは日本市場ではリスクの高い挑戦とされていたが、サービスローンチから2ヶ月間で100人以上の人材業界関係者にプレゼンを行い、理解者を少しずつ増やしていった。登録できる求職者は「年収750万円以上」に限定され、ハイキャリア層に特化したことも新しかった。
その後の展開として、2012年には海外市場向け「REGION UP」、2014年には新卒向け「ニクリーチ」、20代向け「careertrek」、女性向け「BIZREACH Women」、また2016年には採用管理システム「HRMOS」や事業承継M&A支援の「ビズリーチ・サクシード」など、労働市場や社会課題に対応したサービスを次々に展開。多角化とプラットフォーム化を同時に推進するビジネスモデルが特徴である。
革新的ビジネスモデルの構築と進化
収益源の転換がもたらした新たな価値創出
ビズリーチが導入した「求職者課金型」のビジネスモデル。これは当時の日本の人材業界ではかなり異色で、当然ながら社内外で賛否両論あったようです。
でも、転職という人生の大きな決断において「月額料金を払う=本気度が高い」というシグナルにもなる。企業側としても真剣な候補者とだけ接点を持てることで、やり取りの効率も上がるし、マッチングの質も高まるわけです。
 新人ペンタ
新人ペンタえっ!?企業の人から直接メッセージ来るって、ちょっと緊張しますけど、うれしいですね…!
このように、求職者と企業の“お互いの本気度”が高い状態をつくる仕掛けとして、求職者課金は十分に機能していたように思います。
求職者課金型からプラットフォーム収益へ
その後、企業からのスカウト利用料や成功報酬型の人材紹介料も導入され、収益モデルは多角化。結果的に「求人メディア」から「情報プラットフォーム」へと進化しました。
情報が溜まり、蓄積されていくことで、そのプラットフォームの価値自体が増していく。こういう構造、やっぱり強いですね。
人材業界のルールを覆した変革の本質
ダイレクト・リクルーティングと情報の開放性
これまでの日本の採用業界は、企業と求職者の間に人材紹介会社が入り、情報が閉じられた世界だったわけですが、ビズリーチはその構造を変えました。
企業が自ら求職者にアクセスできる仕組み=ダイレクト・リクルーティングを国内でいち早く取り入れたのも革新的でした。LinkedInの国内版と言ってもいいかもしれません。



これはもう、後発のくせに…って言ってられない状況だな。先に動いた者勝ち、ってやつか。
従来大手も巻き込むビズリーチのプラットフォーム力
ビズリーチが凄いのは、創業わずか10年足らずで、リクルートやパーソルといった業界大手すらプラットフォームに巻き込んだ点です。彼らも当初は「ハイクラス市場だけなら影響は限定的」と見ていたフシがありますが、結果的には見誤っていたと言わざるを得ません。
背景にはいくつか理由があります。
- ハイクラス層に特化したサービスは、社内リソース配分やクライアント管理が難しく、対応に時間がかかる
- リクルートは求人広告や紹介業が主力収益源のため、企業が直接候補者にアクセスできる仕組みは従来事業とカニバリ(共食い)を引き起こす
- オープンデータベース化が進むことで、自社が保有する求職者情報の競争優位性が下がる恐れがある
この他社が「手を出したくても出せない」ジレンマの中で、ビズリーチは市場でのポジションを確立。2社の対応が遅れたことで、ビズリーチには市場開拓の“時間的猶予”が与えられたわけです。
さらに、フリーエージェントや個人のヘッドハンターなど、多様なプレイヤーが参画できる点も大きな特徴です。従来の人材紹介会社だけではカバーしきれない領域に、柔軟なマッチングを可能にする場を提供し、エコシステムを築いていったと言えます。



なんか…いつの間にか大手が動かない、動けない間に全部持ってった感じッスね!



2009年時代の人材市場規模は約9兆円で、派遣市場(6兆円)、請負市場(1.5兆円)がビジネスの中心じゃった。求人広告市場・人材紹介事業は比較して大きくないからリクルートもビズリーチという可愛い会社が出来たなくらいにしか思ってなかったんじゃろうな。
リスクの変遷から読み解く事業成長の課題
起業初期の不確実性と現在の競争環境
創業当初は夜な夜な、仲間たちと無給で開発を進めるというベンチャーらしいスタートだったそうです。その当時は「求職者が自分からお金を払うなんて無理でしょ」と否定的な声が多かったとのこと。
でも、少しずつ市場を理解させることで、自らのポジションを築いていった。このフェーズ、どんな業界でも共通していると思います。
今ではLinkedInのような世界的競合も視野に入ってきており、ベンチャーからメガプラットフォームへの成長をどう実現するかが問われているフェーズです。
外部要因への対応力と資金調達の柔軟性
ビズリーチは2016年に、YJキャピタルや楽天、Salesforce Venturesなどから約50億円超の資金を調達。社会的にも注目される企業になっただけでなく、労働人口の減少といった社会課題に対しても、採用管理クラウド「HRMOS」や事業承継支援「ビズリーチ・サクシード」など新規事業で応えてきた。
市場や時代の変化に合わせて柔軟にビジネスの軸を増やせるというのは、スタートアップにとって非常に重要なポイントです。
さいごに
ビズリーチの歩みは、まさに「業界構造を変える挑戦」を体現したものだと思います。
当初は誰にも相手にされなかった市場でも、価値ある仕組みを提示し続けることで、周囲を巻き込み、やがては大手さえも動かすようになる──これは、業種を問わず一つの理想形じゃないでしょうか。
どの業界においても、常識を疑い、顧客や社会にとって「本当に良い形」を探求する姿勢は持ち続けたいですね。



振り返ると当たり前に感じるビジネスも、当時の常識や行動がついていかない中でまっすぐに、静かにやり遂げたビズリーチはさすがじゃて。




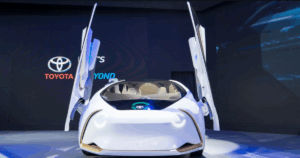





コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 株式会社ビズリーチ 2018 […]