こんにちは、Yatzです!
「ウォルマート・ストアーズ」。
「戦略の実践」として、後発ながら絶大な成長を達成したこの企業は、まさにMBAのテキストでよく出てくる「コストリーダーシップ戦略」の正義を地で行く企業でした。今回は1993年時点のウォルマートの飛躍をもとにその戦略を紐解きます。
1993年時点のウォルマート:成長の原動力と新たな挑戦
ウォルマート・ストアーズは1962年にアーカンソー州で創業。30年後の1993年には、売上6兆円超、店舗数1,800超、従業員数53万人という米国最大規模のディスカウントストアチェーンに成長しました。
その急成長を支えたのは、「Everyday Low Price(EDLP)」を柱に据えた徹底的なローコスト戦略です。以下の3つの要素が戦略の中核を成していました:
- 地方集中出店(ドミナント戦略): 人口5,000〜25,000人の町に集中して出店し、店舗間の距離を短縮。物流効率と広告費を抑えるとともに、地域シェアを独占。
- ITと物流によるオペレーション革新: POSデータを衛星通信で本社に即時送信。クロスドッキング方式で在庫コストを削減しつつ、迅速な商品補充を実現。
- 現場裁量の付与と業務標準化の共存: 店舗ごとの価格設定自由度と、バックヤード業務や陳列手順の標準化を両立させ、効率と柔軟性をバランスよく保つ。
これにより、ウォルマートは営業利益率7.5%を確保し、Kマート(2.7%)やターゲット(6.4%)を大きく上回る実績を誇っていました。
一方で、成長率が鈍化し始めていたのも事実。既存店の売上成長が7〜8%に落ち着き、株価は一時的に22%下落。従来の出店戦略では成長の限界が見え始めていたのです。
こうした状況の中で、ウォルマートは「サムズクラブ(倉庫型店舗)」「スーパーセンター(食品と非食品の融合)」「海外進出」といった新たな成長軸を模索。今後の戦略実行が注目される局面にありました。
徹底的なローコストを支える仕組み
地方集中展開とIT物流で築く鉄壁のオペレーション
ウォルマートの特徴的な出店戦略は、「大都市ではなく、他社が見向きもしない小さな町に集中展開する」というものでした。これは「田舎ドミナント戦略」とも呼ばれ、人口5,000〜25,000人規模の町に集中的に店舗を設けることで、物流や広告といった固定費を地域内で効率的に分散できるモデルです。
 ネコマタ商事
ネコマタ商事よそは「ばらばら」とあちこちに出すらしいですよね…
物流においては「ハブ&スポーク」型のネットワークを構築し、物流センターを拠点にして効率よく商品を各店舗に供給。店舗が地理的に密集しているため、1台のトラックで複数店舗に配送できる仕組みも整っており、逆送時のトラックにも積載をするという徹底ぶりです。
ハブ&スポーク
空港など大規模拠点(ハブ)に貨物を集中させ、そこから各拠点(スポーク)に分散させる輸送方式のこと。
さらに、衛星通信を活用したPOSデータ収集により、売れ筋や在庫の動きをリアルタイムで把握。仕入れ先ともデータを共有し、無駄な在庫や欠品を最小化しています。
このITと物流を一体で運用することで、他社と比べて商品原価や配送コストを圧倒的に抑えることに成功。競合他社の平均より3.7%もコストを下げ、7.5%という高い営業利益率を確保していました。



はいってるぞ…最新技術と手作業の切り替え…
また、価格設定においては、地域特性に応じて店長が柔軟に対応できるよう裁量を持たされており、それでいて商品の陳列方法や業務プロセスは標準化されています。この「自由と統制のバランス」が、現場での迅速な対応と運営の安定性を両立させていました。



許された範囲なら、地域の競合に負けないよう自由に品揃えや価格設定してください。
コストリーダーとしての競争優位
圧倒的な価格優位と独自の差別化戦略
ウォルマートの競争力は、単なる「安さ」では語れません。毎日のように特売チラシを配る他社と異なり、「Everyday Low Price(毎日安い)」というシンプルで力強いポジショニングを取り、顧客に「いつ行っても安い」という安心感を提供していました。
1990年代初頭、ウォルマートはKマートより平均で2.2%、ターゲットより3.7%も安い価格を実現し、カルドアやブラッドリーズなどの地方業者とは20%以上の価格差をつけていました。
しかも、売っている商品はナショナルブランド中心。お客様の信頼を保ちながら、プライベートブランド「サムズ・チョイス」などでは、さらに利益率を確保する仕組みも導入されていました。この商品は見た目は高級感がありながら、価格は競合よりも平均26%も安く、まさに顧客満足と利益確保を両立する施策です。
また、従業員(アソシエーツ)に対するインセンティブ制度や、現場裁量を重んじる文化も、顧客対応の質に直結しています。情報共有、利益配分、持ち株制度などが整備され、従業員が「自分の店」として店舗を運営する意識を持つよう設計されていました。



人を信じるなら、数字も一緒に見せるべきなんだよな
成長の限界と多角化への挑戦
飽和する国内市場と広がる次のフィールド
ウォルマートは1993年以降、既存店の売上成長率が鈍化。地方への出店余地が減少し、これまでの「田舎ドミナント戦略」だけでは成長を維持できなくなってきました。
その中で登場したのが、倉庫型店舗「サムズクラブ」と「スーパーセンター」、そして「海外進出」という多角化の選択肢です。
サムズクラブは、法人顧客や大家族向けに大量購入を促すモデル。これにより購買単価が上がり、少ない顧客数でも売上を確保できます。スーパーセンターでは食品と非食品を融合し、日常の買い物をすべて一カ所で完結できる「ワンストップショッピング」を実現。
一方、海外市場ではメキシコなどを皮切りに出店を加速。米国市場の飽和を補うための戦略的な一手でした。
もちろん、これらの多角化にはリスクもあります。特に、スーパーセンターのオペレーションは複雑化しがちで、物流・在庫管理の難度が上がります。ただ、ウォルマートは既に持っていたIT・物流の基盤を新業態にも展開することで、効率性を維持しつつ新たな成長軸を模索していました。
スーパーセンター戦略の成否を探る
食品+非食品=次なる顧客価値
スーパーセンターは、ウォルマートが次の成長を模索する中で登場した新業態です。特徴は、生鮮食品や日用品などの高頻度購買商品と、衣料・家電などの低頻度商品の融合。
これにより、顧客は「ついで買い」の機会を得て、一度の買い物で複数カテゴリの商品を購入するようになります。これは、客単価の上昇だけでなく、来店頻度の向上にも寄与します。



僕、冷蔵庫買いに行ったのに、おやつと靴下も買っちゃいました…
また、店舗設計や顧客動線も緻密に設計され、食品売り場から自然と非食品に誘導される導線が作られています。これにより、「必要なもの+α」の買い物を自然に促進。
競合他社との差別化という点でも、「安いだけじゃない便利さ」を打ち出したこの業態は、都市部でも確実に支持を集め始めていました。
さいごに
ウォルマートの躍進は、「コストリーダーシップ戦略」を教科書通りに実践しただけではありません。
出店戦略、物流、IT、価格設定、ブランド管理、従業員マネジメント、どれもが一貫した思想のもとに構築されていました。そして、成長の限界が見えてきたタイミングで、多角化や業態転換にも取り組み、持続的な成長のための道筋を模索。
これはまさに「戦略の定石」を柔軟に活かしつつ、実務に根差した応用力があったからこそできたこと。
学んだ理論を「どこまで本気で、どこまで現場に落とし込めるか?」その問いに答えるリアルな事例でした。



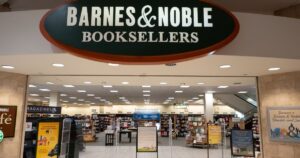






コメント