すみません。他にもサイト作るかもしれないので、My備忘録・Myナレッジとして作っています。
ブログを作って、サチコさん(Google Search Console)を見るようになると思うんです。
「全然、検索されてないやんけ!」と。
で、SEOを意識しないとと思うわけですが、たくさん記事書いた後だと修正も大変ということで、先にブログを科学的に抑える必要があると思ったわけです。今回は、最適な投稿頻度について備忘メモします。
結論:SEO効果を最大化したいなら「1週間おき」に質の高い記事を継続的に公開するのがベスト
ブログ運営において、SEO対策として「投稿(更新)頻度をどうするか」は多くの方が直面する悩みです。
例えば、10記事のストックがあるとすると、
一括投稿?同じ日付で時間をずらして投稿?1日ずつ?1週間おき?と考えるわけです。
気持ちとしては早く公開したい!という思いも当然あります。
結論から言えば、10記事を一括で投稿するよりも、「1週間おき」に高品質な記事を公開していく戦略が最も効果的らしいです。
Googleは検索順位の決定において、更新頻度そのものを直接の評価指標にはしていません。評価されるのは、あくまで「コンテンツの質」と「ユーザーの検索意図への貢献度」。
つまり、「毎日更新しているから上位表示される」わけではないということです。
しかしながら、更新頻度はSEOに間接的に影響を与える側面が存在します。たとえば、クロール頻度やサイトへの信頼性、エンゲージメントの促進といった要素です。この記事では、その関係性を具体的に解説したうえで、10記事を用意したときに「どのように公開すれば最もSEOに効果があるのか」を検討していきます。
ブログの更新頻度がSEOに与える直接・間接の影響
Googleは更新頻度を“直接評価”していない
Googleの検索品質ガイドラインや公式発言において、更新頻度はランキングの直接的な評価要素ではありません。Googleのジョン・ミューラー氏も繰り返し、
「頻繁に更新しているからといって、それだけでランキングが上がるわけではない」
と述べています。
つまり、「更新している=良いサイト」ではないのです。重要なのは、ユーザーの検索意図を正確に捉え、それに対して価値ある情報を提供しているかどうか。
更新頻度が間接的に影響を与える3つのポイント
① クローラーの巡回頻度
サイトが定期的に更新されると、Googleのクローラー(Googlebot)が頻繁に訪問するようになります。これは「クローラビリティ」の向上と呼ばれ、結果として新しい記事が早くインデックスされ、検索結果に表示されやすくなるのです。
ただし、これは質の高いコンテンツであることが前提。質が低いコンテンツを量産しても、かえって評価を落とすリスクがあります。
② ユーザーエンゲージメントの向上
定期的に新しい記事が公開されると、ユーザーは「このサイトは活発に運営されている」と感じ、再訪問やSNSシェアなどの行動に繋がります。これが滞在時間の延長や直帰率の低下など、間接的なSEO評価ポイントにつながります。
③ コンテンツの鮮度(Freshness)
Googleは検索クエリの種類によって「情報の鮮度」を重視します。たとえば、ニュースや時事性の高いテーマでは、新しい情報が優先的に評価される傾向があります。一方で、普遍的なノウハウ系の記事は「鮮度」よりも「網羅性」や「深さ」が重視されます。
「10記事」を用意したときの公開戦略の比較
ここでは、10記事を公開する際に考えられる4つのシナリオを表で比較してみました。
| 公開方法 | SEO効果 | ユーザー行動 | 推奨度 |
|---|---|---|---|
| 一括公開 | クロール遅延・スパムリスクあり | 情報飽和で分散される | ❌ 非推奨 |
| 同日分散 | 限定的な効果 | 飽和リスクはやや軽減 | △ 条件付き |
| 1日おきにUP | クローラーに好影響 | エンゲージメント促進 | ◯ 推奨 |
| 1週間おきにUP | E-E-A-T強化・継続性確保 | 安定したユーザー習慣の形成 | ◎ 最適 |
E-E-A-T:
Googleの検索品質評価ガイドラインで使われている評価基準の1つで、次の4つの要素の頭文字をとったものです。
‐Experience(経験):実体験に基づいて書かれているか
‐Expertise(専門性):専門的な知識に基づいて書かれているか
‐Authoritativeness(権威性):執筆者やサイト自体が信頼されているか(第三者評価)
‐Trustworthiness(信頼性):情報の正確さ・安全性・透明性があるか
「1週間おき更新」が最も効果的な理由
継続性と品質維持の両立が可能
1週間に1本であれば、記事1本にかけられる時間が十分にあり、リサーチ・構成・校正に丁寧に取り組めます。結果的に「E-E-A-T」(経験・専門性・権威性・信頼性)を満たした質の高いコンテンツが生まれます。
無理のない運営で長期的な信頼を構築
更新頻度はあくまで「続けられるペース」であることが重要です。無理な毎日更新で燃え尽きるよりも、着実に週1更新を続ける方が、結果としてSEOに有利です。
プロモーション期間が確保できる
SNSでの拡散、メールマガジンでの紹介、既存記事との内部リンク構築など、1本の記事をじっくり育てる時間が取れます。
特に重要:記事の鮮度を保つ「リライト戦略」
新しい記事を投稿するだけでなく、既存記事の更新(リライト)もSEOに効果があります。
- 定期的に最新情報に更新
- 検索意図の変化に対応
- 内部リンクや関連キーワードの見直し
「最終更新日」が新しいとユーザーのクリック率(CTR)も上がる傾向があり、間接的にSEO評価にもつながります。
コンテンツのジャンルごとに最適な更新頻度は違う
| ブログの種類 | 鮮度の重要性 | 更新頻度の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ニュース・時事系 | 非常に高い | 毎日〜週3回 | トレンド重視 |
| 専門ハウツー系 | 中〜高 | 週1〜2回 | 深さが大事 |
| 趣味・ライフログ系 | 中〜低 | 週1回〜月2回 | 継続性が重要 |
| 商品レビュー・企業系 | 中 | 週1回程度 | 品質と信頼性 |
競合やリソースに応じて戦略を調整が必要
以下の点を考慮して、更新戦略を設計しましょう:
- 自社のブログ目的(認知?集客?教育?)
- 執筆リソース(人員、時間、予算)
- 競合の投稿頻度と内容
- 記事ごとの検索意図の違い(速報性 vs 網羅性)
わたしは、特に競合があるわけでもなく、という状況なので自分の都合で設計します。
補足:トピッククラスター戦略を用いた構造設計も有効
もし10記事がある特定テーマに関連するなら、それぞれを「サブ記事」としてまとめ、「柱記事(ピラーページ)」と内部リンクで結びましょう。これにより、Googleに対して「専門性が高いサイト」と認識されやすくなり、E-E-A-Tの評価が高まります。
まとめ:SEOにおける“正しい更新頻度”とは
- 更新頻度は「直接」評価されないが、「間接的」には大きく影響する
- 無理な高頻度より、“質と継続性”の両立が最重要
- 10記事を一括公開するより、1週間おきに高品質記事を計画的に公開する戦略が最もおすすめ
- コンテンツの種類や読者のニーズ、リソース状況によって柔軟に調整を
- 「続けられる」ことが、最終的にSEO成功のカギになる
SEOはマラソンとはよく言われます。
すぐ辞めちゃう人がいるのも短期での結果を求めるからだとも聞いています。とりあえず1年走ってみた結果を踏まえてその先を考えようと思います。

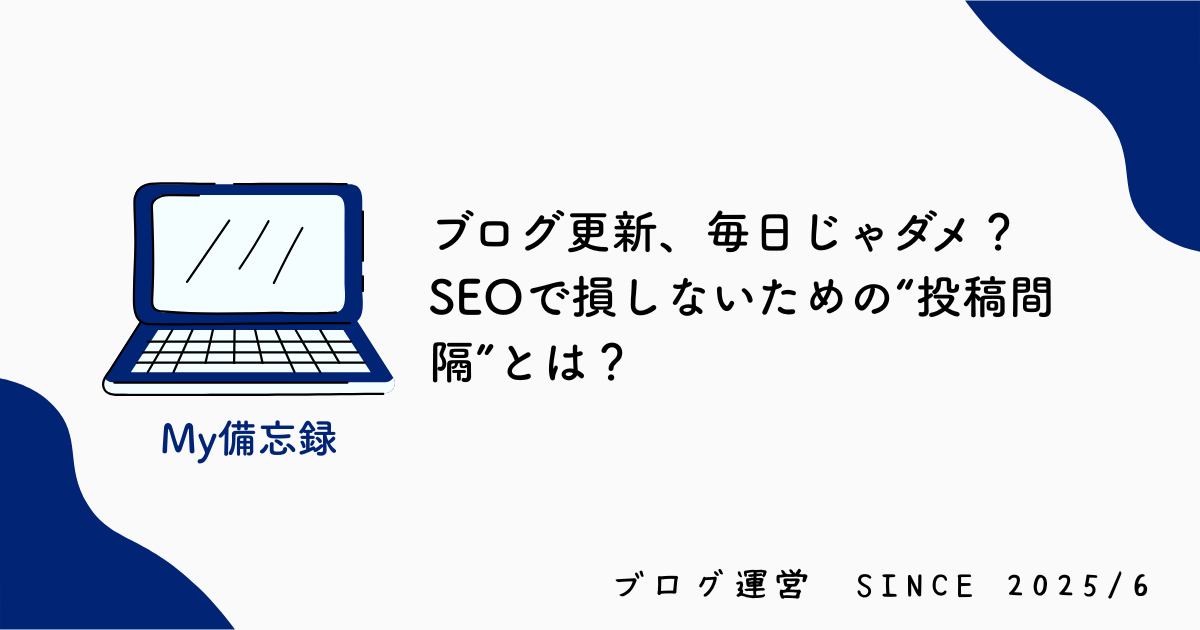
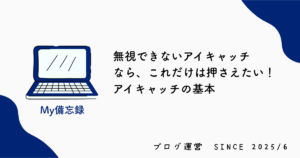
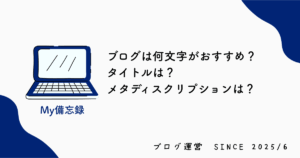





コメント