こんにちは、Yatzです!
1990年代の欧州航空市場は、EUの規制緩和によって一気に自由化され、多くの新規参入と既存大手の低価格路線進出が重なり、過当競争に突入しました。ライアンエアは倒産寸前から、固定費・変動費の両面を大胆に削減し、利益を生むバリューチェーンを構築することでV字回復。1998年には営業利益率23%という業界最高水準を叩き出しました。
見事な復活劇を紐解きます。
倒産寸前からのV字回復
ライアンエアは1991年、資金繰り悪化で倒産寸前に陥りましたが、マイケル・オリアリー副社長(当時29歳)のもと、過剰なサービスを廃止し、コスト構造を抜本的に見直しました。無料軽食やエアブリッジ利用をやめ、周辺空港を活用して着陸料を削減。さらに、機材をボーイング737に統一し整備コストを低下させました。
1992年に黒字転換し、その後7年間連続で利益を確保。1999年時点で、アイルランド・英国・欧州大陸の計33空港へ、1日約150便を運航。ダブリン〜ロンドン間のマーケットシェアは約3分の1、アイルランド〜英国地方都市間では50%超を占めました。顧客の70〜75%は観光客、25〜30%は中小企業の出張客で、航空運賃は競合より最大50%安く設定。
一方、1993年のEU自由化により参入が急増(1993〜98年で131社参入→57社存続)し、競争は激化。短距離は鉄道・バスが競合し、長距離は航空優位という構造でした。ライアンエアは「路線は需要倍増が見込める場合のみ参入」という選択基準を徹底し、機内販売・広告・レンタカー紹介料など補助収入も拡大。従業員1,200人の大半に成果連動報酬とストックオプションを導入し、柔軟な組織運営を維持しました。
結果として1998年の営業利益率は23%と高水準を達成し、同時期のBA(ブリティッシュ・エアウェイズ)6.9%を大きく上回りました。
5 Forces分析(規制緩和で加速する空のデスマッチ)
- 新規参入の脅威
- 規制緩和で参入は容易化
- 外注利用で初期投資削減が可能
- ただし機材購入・発着枠確保は依然ハードル高
- 業界内競争
- 大手フラッグキャリアとLCCの競争
- 格安同士の価格戦争も激化
- ダンピング的な運賃設定が常態化
- 代替手段の脅威
- 短距離は高速鉄道・長距離バスが競合
- 長距離では航空優位
- サプライヤーの交渉力
- 空港利用料・燃料費は規模によって交渉力変化
- 周辺空港利用で発着料低減
- 買い手(顧客)の交渉力
- 価格重視で忠誠度低い
- ウェブ予約普及で乗り換え容易
- 格安運賃が需要創出
特に、新規参入の脅威は大きく、業界内競争は激化しており、買い手である顧客もスイッチングコストは低く、通常だと魅力的な業界とは言えないわけです。
 ブル取締役
ブル取締役規制緩和は翼をくれるが、そのぶん空中戦は血みどろになる
バリューチェーン分析(全工程が利益を生む仕組み)
それでも、ライアンエアは勝負に出るわけです。
とにかく、固定費と変動費を最大限に減らしながら路線拡大、乗客率向上で剝離ながら規模の経済も利かせながら徐々に盛返す方法にかけるわけです。
①調達・メンテナンス➡②マーケティング・販売➡③運航➡④顧客サービス
のバリューチェーンの流れを見ていきます。
調達・メンテナンス
- B737統一で整備・教育コスト削減
- エアブリッジ不使用で固定費削減
- 外注整備・地上業務で人件費抑制
マーケティング・販売
- WEB直販・コールセンターで代理店手数料ゼロ
- 広告費を抑え口コミ・ブランド力活用
- 機体・機内広告による補助収入化
運行
- 周辺空港利用で着陸料削減+定時運航率向上
- 折り返し25分、高稼働で固定費を薄める
- 機材稼働率向上で1機当たり売上最大化
顧客サービス
- 無料サービス廃止で変動費圧縮
- 機内販売・広告で利益化
- 成果連動報酬で従業員コスト意識向上



節約を積み重ねると、それは戦略になるわけですね。
欧州LCC戦争で生き残った者の条件
ライアンエアだけでなく、規制緩和の流れでデボンエア(Debonair)、ゴー(Go)、ヴァージン・エクスプレス(Virgin Express)、イージージェット(easyJet)など後発LCCも続々参入してきます。その中でもライアンエアはしっかりとその地位を確立していきます。
ライアンエアの強み(後発との決定的な違い)
- 路線選定の精度と“選択と集中”
- 需要が倍増すると見込める路線にしか参入しない。
- 周辺空港を活用し、大手や後発との価格消耗戦を避ける。
- 結果として、ダブリン〜ロンドン間ではシェア約3割、地方都市間では5割超を確保。
- バリューチェーン全体でのコスト優位
- 固定費削減:機材統一(B737)、エアブリッジ不使用、周辺空港利用による着陸料削減。
- 変動費削減:機内無料サービス廃止、外部委託で地上業務の人件費圧縮。
- 収益化の工夫:広告・機内販売・レンタカー紹介料などで売上の5〜7%を補完。
- 高稼働オペレーション
- 折り返し時間25分で機材稼働率を最大化。
- 1機あたりの飛行時間は1992年4.13時間→1999年6.47時間(約1.6倍)。
- 組織運営とインセンティブ制度
- 成果連動報酬・ストックオプションで従業員のコスト意識と効率性を高める。
- 年功序列ではなく能力評価、内部昇進を基本とする柔軟な体制。
なぜ後発LCCは苦戦したのか
- コスト構造の非効率:複数機材を運用して整備・訓練コストが高騰。
- 路線戦略の不明確さ:競合が多い主要空港に集中し、発着料や遅延リスク増大。
- 規模・資本力不足:短期間でのネットワーク拡大が難しく、価格競争で体力を消耗。
要するに、ライアンエアは「低価格」という表面的な特徴の裏に、徹底したコスト構造改革と、競争を避ける市場選びを組み合わせていたことが最大の強みです。
このため、同じLCCでも後発組とは収益構造そのものが違い、競争環境の荒波にも耐えられたのです。
さいごに
ライアンエアは、バリューチェーン全体を「利益創出構造」に変え、規制緩和後の混乱市場で高収益を維持しました。コスト削減と収益化を両立する仕組みは、他業界でも応用可能な教訓です。



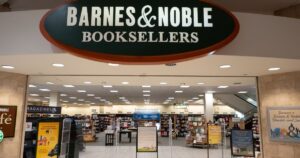






コメント