こんにちは、Yatzです!
1980年代後半、欧州の空はまだ「フラッグ・キャリア」という名の要塞に守られていました。国営航空会社による独占、IATAやプーリング協定で固められた価格と路線、そして国益を背景にした政治力。そこに、アイルランドの新興企業ライアンエアが乗り込んだのは1985年。彼らの武器は、分かりやすい一律料金98アイルランド・ポンドと、既存大手並みの快適さでした。
最初は順風満帆。しかし、規制緩和の波と競争激化が同時に押し寄せた市場で、彼らはわずか数年で破綻寸前に追い込まれます。今回は、PEST視点での外部環境分析、コスト構造の裏側、そしてライアンエアが辿った戦略の成否を振り返ります。
欧州空の逆風とライアンエアの挑戦記
1980年代半ば、ヨーロッパ航空業界は国営の「フラッグ・キャリア」が市場を支配していた。第二次世界大戦後に整備された規制体制のもと、IATA(国際航空運送協会)やプーリング協定によって、価格・路線・運航権が厳格に管理され、各国航空会社は国益を背負った存在として運営されていた。価格競争はほぼ存在せず、国内便や短距離国際便も高額で推移していた。
1984年、欧州委員会は航空市場の規制緩和に着手。1992年に単一市場を実現する構想が示され、路線開設や価格設定の自由度が徐々に拡大していった。英国ではサッチャー政権下で民営化が進み、BA(ブリティッシュ・エアウェイズ)は1987年に株式公開。高コスト体質の改善を経て利益を回復させたが、それでも固定費率は高く、需給変動による収益変動が大きかった。
アイルランドの新興企業ライアンエアは1985年、ウォーターフォード—ロンドン(ガトウィック)便を14席ターボプロップ機1機で開設。翌1986年には、ドル箱路線であるダブリン—ロンドン(ルートン)に98アイルランド・ポンドの一律料金で参入した。当時、BAとエアリンガスが設定していた往復料金は208ポンド(制限なし最安値)で、1か月前予約の割引でも99ポンド。ライアンエアは「既存大手並みのサービス+低価格」を武器に、ビジネス客・観光客・鉄道やフェリー利用者まで全方位を狙った。
就航発表直後、BAとエアリンガスは95ポンドに値下げし、ライアンは94.99ポンドで対抗。1989年には価格が70ポンドまで下がり、業界全体の収益性が悪化した。初期のライアンエアは座席稼働率がほぼ満席で、顧客から「価格の英雄」として支持を集めたが、マンチェスター、リバプール、グラスゴーなどへの急速な路線拡大により、経営システムと資金管理が追いつかなくなる。1988年には600万ポンド、1989年には450万ポンドの赤字を計上した。
アイルランド政府は1989年に路線区分政策を導入し、ヒースローやガトウィックなど主要空港はエアリンガス専用、ルートンやスタンステッドはライアンエア専用としたが、収益改善には至らなかった。1991年1月、ダブリン空港使用料34,000ポンドすら支払えず、破綻寸前に陥った。
当時のコスト構造を見ると、BAは固定費126I£、変動費29I£で損益分岐点は155I£。ライアンエアは米国並みの運航効率と満席運航を前提にすれば、固定費70.9I£、変動費23.5I£で合計94.4I£に抑えられると試算された。
※固定費は、人件費、減価償却費、燃料費、整備費、リース料、宿泊設備などで、変動費は着陸料が中心。販売費や手数料・機内食は固定・変動が半々と試算。
このような高固定費ビジネスでは、利益を出すには①高稼働率で固定費を分散、②固定費を変動費化(外注や業績連動給)、③償却済み設備の活用、④直販比率の向上などの対策が必要となってくる。顧客分析では、ビジネス客は利便性やサービスを重視するため価格競争では取り込みにくく、価格志向の強い観光客や他交通機関利用者が主要ターゲットとなる。
ライアンエアは当初「安くて快適」の全方位戦略で市場を揺さぶったが、価格下落と急拡大による固定費負担増、資金管理不備が重なり、わずか数年で経営危機に直面。生き残りのため、米サウスウエスト航空型の徹底LCC化、高価格ビジネスクラス導入、米系航空会社のフィーダー化などの選択肢が議論された。最終的にはLCCモデルへの転換が、後の復活への道となった。
外部環境と業界特性(ライアンエア視点でのPEST分析)
- 政治(P)
欧州委員会の規制緩和(1984年以降):新規参入の障壁が下がり、ライアンエアにとっては最大の追い風。国際線やドル箱路線へのアクセスが可能になる。
BA民営化(1987年):大手が効率化・収益性重視にシフト。顧客サービスや価格戦略が洗練される可能性が高く、競争が一層厳しくなる。
→ ライアンエア視点では短期的にネガティブ。理由は、国営時代より俊敏に値下げ対応できるBAが相手になる。 - 経済(E)
燃料費高騰:変動費の増加要因。LCC化で固定費は抑えられても、燃料費はほぼ制御不能なのでリスク。
景気変動:不況時は価格重視層が増え、ライアンエアにはプラスだが、需要全体は縮小する。 - 社会(S)
低価格志向の高まり:観光客・フェリーや鉄道利用者層の航空移行が進み、ライアンエアのターゲット市場が拡大する。
→ 明確なプラス要因。 - 技術(T)
予約システム普及:座席稼働率の管理や直販強化につながる。小規模でも導入可能なので、プラス要因。
ライアンエアの場合、特に規制緩和(P)と低価格志向(S)が大きなプラス要因ですが一方で、BA民営化(P)と燃料費高騰(E)がリスク要因と考えられますね。
コスト構造と利益確保の条件
BAのコスト構造では、固定費126I£、変動費29I£、合計155I£。
固定費ビジネスの戦略鉄則
- 乗客数を最大化:固定費は乗客数で割って負担を軽くする(満席運航)。
- 固定費→変動費化:外注、人件費の業績連動化、設備のシェアリング。
- 償却済み設備の活用:減価償却費を抑える。
- 販売チャネル効率化:代理店依存を減らし直販比率を上げる。
といったことが考えられますが、ここでは王道の満席での運航を目指すことを想定すると、固定費70.9I£、変動費23.5I£、合計94.4I£まで低減可能と試算されます。
 新人ペンタ
新人ペンタつまり、座席が空いてるだけで損が増えるってことですか…



そう、空席は固定費の“空回り”だね
価格一本足で満席を狙う
当時のターゲット候補は以下の3層
- ビジネス客(年間約50万人)
ニーズ:移動の速度、空港アクセスの利便性、柔軟なスケジュール変更 - 観光客(年間約75万人)
ニーズ:何よりも低価格、サービスは最低限で可 - フェリー・鉄道利用客(年間約75万人)
ニーズ:時間よりも価格優先、長時間移動も許容
このうち、主要顧客となり得るのは価格志向が強い観光客と、他交通機関からの移行組でした。ビジネス客は市場規模は大きいものの、低価格だけで引き寄せることは難しく、利便性やサービスが同等でなければ離脱してしまいます。
参入当初のライアンエアは、BAやエアリンガス並みの快適さと柔軟性を維持しながら低価格を打ち出しました。これは「全方位を価格一本足で取る」という挑戦でもありました。
しかし、このアプローチは高固定費の構造と相性が悪く、満席を続けなければ収益は安定しません。特にビジネス客層まで囲い込むためのサービス維持は、コスト削減の余地を削り、後の財務圧迫へとつながっていきました。



全員に好かれようとすると、経費が先に好き放題するもんだよ
戦略の岐路―ライアンエアはなぜ失速したのか
参入初期には顧客の圧倒的支持を集め、市場に大きな衝撃を与えたライアンエア。しかし、空港使用料も払えない状況まで追い込まれます。その理由を改めて考えると、以下のようなことが挙げられます。
- 競争環境の見誤り
- BA民営化により、大手は価格引き下げや効率化への対応が迅速化。従来の「動きが遅い国営企業」という弱点が消え、ライアンエアの価格優位が一気に縮小した。
- 全方位ターゲティングの弊害
- ビジネス客・観光客・他交通機関利用者をすべて狙った結果、サービス品質をある程度維持せざるを得ず、固定費削減が中途半端になった。
- 高固定費構造のままの急拡大
- マンチェスターやリバプールなど新路線を次々開設。座席稼働率の維持が難しくなり、固定費負担が増大。
- 資金管理・運営体制の脆弱さ
- 赤字累積(1988年600万I£、1989年450万I£)に加え、1991年には空港使用料34,000I£を支払えない事態に。
判断は本当に間違いだったのか?
結果として失敗には至ったものの、1980年代半ばという市場環境を考えれば、「低価格で参入し、大手の価格カルテルを崩す」という選択自体は合理的でした。
実際、規制緩和初期の隙を突いて市場シェアを獲得できたのは事実です。
問題は、その後の競争局面の変化への対応の遅さです。BA民営化後の俊敏な値下げや、他のLCCの台頭を受けて、早期にコスト構造をLCC型へ転換できなかったことが命取りとなりました。
戦略的教訓
- 参入初期の成功モデルを長く引きずらない:市場環境が変われば戦略の前提も変わる。
- 固定費ビジネスは稼働率とターゲット絞り込みが命:全方位戦略は中途半端なコスト構造を招く。
- 資金管理は拡大戦略の生命線:キャッシュアウトが早ければ戦略転換の猶予がない。
ライアンエアはこの失敗から学び、その後サウスウエスト航空型の徹底LCCモデルに舵を切り、現在の地位を築きました。A・Bケースで描かれた失敗は、言い換えれば「LCCのライアンエア」が誕生するための通過儀礼だったともいえます。



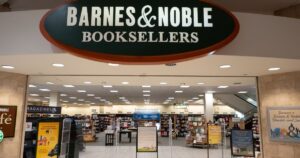






コメント