こんにちは、Yatzです!
Day3では、テスラに対抗してトヨタのケースが2つ登場します。
まずは、トヨタ2017として、トヨタ自動車の「コネクティッドカンパニー」が直面した課題とITジャイアントとの複雑な関係、そしてプラットフォーム競争の現状について考えていきます。
ケースの要約
トヨタ自動車は2016年3月、将来の自動車業界の変化に備えた大規模な組織改革を行い7つの「製品軸カンパニー」を設置。このうちの1つ「コネクティッドカンパニー」は、ICTやビッグデータを活用した新たな価値創造を目指す戦略的部署として設けられ、専務役員の友山茂樹氏がプレジデントに就任しました。
2017年時点のトヨタは、為替の追い風もあり業績は好調。グローバル販売台数でフォルクスワーゲンと1位・2位を争い、ハイブリッド車のラインナップ拡充や次世代アーキテクチャ「TNGA」を採用した新型プリウス、グローバル戦略車CH-Rなどを投入し、市場でも一定の成功を収めていました。
しかしその裏では、いくつかの不安要素が顕在化していました。たとえば、イギリスやフランスなどでは2040年を目標に「新車販売の100%EV化」を宣言。さらにシェアリングエコノミーの浸透により、個人が車を所有するという従来のビジネスモデルそのものが崩れかねない危機感もありました。
この変化に対し、友山氏は「コネクティッドカー」こそがトヨタの次の成長の鍵であると捉え、「三本の矢」戦略を推進します。
- すべてのクルマのコネクティッド化(DCM搭載)
2020年までに日米で販売される全トヨタ・レクサス車に、データ通信モジュール(DCM)を標準搭載。通信を通じて車両情報をリアルタイムで収集・送信し、顧客サービスやビジネス変革に役立てる。 - ビッグデータの活用
走行情報やドライバーの利用状況を分析し、渋滞予測、整備提案、保険料変動など、付加価値を生み出すサービスへと展開。 - 異業種連携による新モビリティサービス創出
KDDI、マイクロソフト、Uber(ライドシェア)、GetAround(カーシェア)などと提携し、オープンプラットフォーム「Mobility Service Platform(MSPF)」を通じて、新たな移動体験を設計。
同時に、ソフトウェア・クラウド・AIといった領域ではGoogleやAppleなどのITジャイアントが大きな競争相手となります。特にGoogleは、Android OSやGoogle Mapsを通じて得られる膨大なユーザーデータを武器に、精度の高い広告配信や顧客分析を展開。2016年時点の営業利益率もトヨタの7.6%に対し、Appleは26.76%、Google(Alphabet)は26.27%、Facebookに至っては44.96%と圧倒的。時価総額でもトヨタは2〜3倍の開きがあります。
さらに、コネクティッド化によりサプライチェーンも大きく変化。高級車では電子部品のコストが約30%、ハイブリッド車では約50%を占め、かつその中の40%が制御用ソフトウェア(ソースコード)で構成されるとされています。従来のサプライヤーとは異なり、DCM、クラウド、センターサーバー、アプリ、通信費などITベースの新たなコスト構造にシフトしていく必要がありました。
これに対応すべく、トヨタは自らプラットフォーム構築に取り組み、手の内化(内製化)に注力。G-BOOK、I-Connect、Toyota Smart Centerなどを自社で開発・運用することで、ITジャイアントに依存しない体制づくりを目指しました。
一方で、Gazooから続く自前主義はスピード感の面で限界もあり、最先端のAIやクラウド技術を持つIT企業との連携は避けられないジレンマも抱えています。特にAppleやGoogleが月額課金プラットフォームを握る中、彼らに支配されることなくどうやってトヨタの独自性を保つかが、今後の命運を握ります。
最後に、豊田章男社長は2018年のCESで「トヨタはモビリティカンパニーに変わる」と宣言。全車種に電動化オプションを導入し、2025年までにEV/電動車対応を完了させる計画を発表。e-Paletteなどの取り組みも含め、ハードからサービスへの脱皮を図っています。
コネクティッドカンパニーの挑戦:変革期におけるリーダーの課題
クルマの未来像を描くプレジデントの視座
友山プレジデントは、「車を持つ」ことの価値が変化する中で、トヨタの持続的成長には“モビリティサービスプラットフォーム”の構築が不可欠だと認識していました。実際、2040年までに新車販売の100%EV化を目指す国もあり、クルマの役割は「移動の道具」から「情報とサービスのハブ」へと変貌しつつあります。
 ブル取締役
ブル取締役モノづくりで一流でも、サービスで一流かはまた別の話だな
トヨタの強みと変革圧力の交差点
ハイブリッド車や品質力といった従来の武器は、データやソフトウェア主導の世界では十分ではありません。自動運転やシェアリングが進めば、個人所有の前提が崩れることになり、トヨタにとっての「成功の定義」すら変わる可能性があります。



えっ…じゃあ僕が10年ローンで買ったプリウス、意味なくなるんですか?
ITジャイアントとの接近と葛藤:パートナーか競争相手か
提携による技術革新とスピード感の獲得
トヨタはマイクロソフトとの提携を進め、北米に「トヨタコネクティッド」社を設立。また、KDDIやUber、GetAroundといったプレイヤーとも協業。これは、従来の自前主義では実現できないスピード感と柔軟性を得るための選択でした。



わあ、Uberと提携ですか!すごいスピードですね!
独自性・主導権を守る難しさとリスク
ただし、AppleやGoogleのようなプラットフォームプレイヤーと手を組む場合、課金システムやデータ基盤を握られる危険性があります。特に、Googleのように「検索」「地図」「Android」と複数の接点を持つ企業に主導権を握られれば、トヨタは“下請け”のような立場に甘んじるリスクもあります。
トヨタはプラットフォーム競争に勝てるか
自動車メーカーの役割再定義とモビリティ企業への進化
トヨタは「e-Palette」という移動型プラットフォームを提唱し、AmazonやPizza Hutとも連携を模索中。このようにクルマをサービスの起点とする発想は先進的ですが、「クルマを作る」ことと「プラットフォームを握る」ことは別のゲームです。



ハードは作れても、“場”を制するのはまた別の筋力やで
手の内化による競争力確保と今後の鍵
トヨタはG-BOOK、I-Connectといった自社サービスを通じて、データの内製化・手の内化を進めてきました。ただし、AIやセンターサーバーの進化スピードを考えると、ITジャイアントに対抗するには開発速度と投資規模が圧倒的に不足しているように見えます。
結果として、協業は避けられずとも、独自性を保つ領域をどこに設定するのかが、今後の命運を握ることになりそうです。
さいごに 「強み」と「変化」のはざまで──トヨタの次なる選択肢は?
トヨタは「モビリティ企業」への転換を掲げ、新たな成長モデルの構築を目指していますが、その道のりは想像以上に険しそうです。競争相手は、同業の自動車メーカーではなく、GoogleやAmazon、Appleといった“異種格闘技”の猛者たち。
従来の勝ちパターンが通用しない中で、どうトヨタらしさを活かしていくか、自分自身の仕事に置き換えても考えさせられるテーマで、日本人としてトヨタには勝ってもらいたいと思いながらどのようになっていくのかワクワクした気持ちになりました。








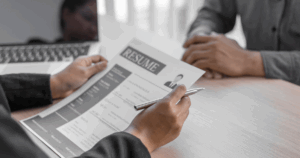

コメント