こんにちは、Yatzです!
高齢化と人口減少が進む日本において、医療現場では「慢性的な人手不足」と「医療の質の確保」という二律背反のような課題に直面しています。とくに高度な判断とスピードが求められる集中治療領域(ICU)では、現場スタッフの負担は年々増加し、離職や教育の停滞といった“負のスパイラル”に悩まされているのが現実です。
そんな中、フィリップス・ジャパンが提案する「遠隔集中治療支援ソリューション(Tele-ICU)」は、テクノロジーと医療の融合によって、こうした課題に一石を投じようとしています。
フィリップス・ジャパンの挑戦
2021年、フィリップス・ジャパンは「遠隔集中治療支援ソリューション」の日本市場展開に苦戦していました。アメリカでは、ICUベッドの15%以上がTele-ICUの支援下にあり、導入により死亡率20%低下、在室時間30%短縮などの成果が報告される一方、日本では医療制度や文化の違いから展開に課題が多く存在していました。
フィリップス・ジャパンの桜井氏は、プロジェクト停止の危機を乗り越え、改めて事業化へ動き出します。米国と同様の「ライセンスモデル」だけでなく、中小病院でも導入できるよう「支援センターモデル」を考案。また、現場スタッフとのワークショップを通じて課題を可視化し、導入価値を伝えるという“現場起点”の導入ステップを構築しました。
最終的には、薬事認証の取得とトップ承認を経て、販売開始にこぎつけるに至りますが、アメリカとは異なるインフラ事情や収益構造、診療報酬体系といった日本特有のハードルに直面しつつも、遠隔支援を通じた臨床改革に向けた一歩を踏み出した実例となっています。
高齢化社会への対応とソリューションの価値
多拠点支援を可能にする臨床支援技術
このソリューションは、支援センターから最大150人の患者を一括支援する仕組みで、遠隔地にある病院のICUに対して、医師や看護師、事務スタッフが24時間365日体制で対応します。電子カルテや生体情報モニタから得られるデータをAIが分析し、患者の重症度や死亡リスクを予測。要介入優先度を明確にすることで、見落としのない迅速な判断が可能になります。
また、音声・映像でベッドサイドとリアルタイムにつながることで、遠隔でも“その場”にいるような支援が可能に。医師不足に悩む地域医療への貢献や、複数拠点を横断的にサポートする体制が現実のものとなっています。

† 出典元:フィリップス・ジャパン
医療資源の有効活用とアウトカムの向上
この支援体制の導入によって、アメリカでは患者死亡率20%低下、ICU在室時間30%短縮といった実績が報告されています。また、患者1人あたりの医療費は年間約55万円削減されたとされ、コスト削減の面でも非常に効果的です。
 ゴリ係長
ゴリ係長労力の最適化ってやつだな。患者さんもスタッフも助かる仕組みだ
人とテクノロジー、プロセスを組み合わせることで、質の高い医療の持続可能性を実現する──これがTele-ICUの最大の価値なのだと感じました。
アメリカ市場における成功とその理由
柔軟な医療制度と成果重視の文化
アメリカの医療制度は基本的に民間保険主導で、病院ごとの収益性や診療成績が厳しく問われます。この「成果主義」の文化は、遠隔支援ソリューションのような“アウトカム改善型”のサービスと非常に相性が良いのです。
また、Tele-ICUの導入により在院日数を短縮し、医療費を削減できれば、保険会社や医療機関にとって大きな経済的メリットになります。実際に、支援サービスを他院に提供し“ビジネス化”している病院も存在しており、遠隔支援が一種の収益源としても成立しています。
支援のビジネスモデルと医療機関の営利志向
アメリカでは、導入から運用、保守までを明確にパッケージ化し、顧客(病院)にライセンスとして提供しています。医療機関もITやインフラに精通しており、各ベンダーとの直接契約によって導入コストを抑える文化が定着しています。



“成果出せるなら導入する”。理にかなってるな。うちもライセンス検討するか。
フィリップスが長年にわたり蓄積してきたアルゴリズムや実績も信頼を後押しし、Tele-ICU市場ではトップシェアを維持しているとのことです。
日本市場への展開を阻む壁
医療制度・診療報酬体系が及ぼす影響
一方、日本では国民皆保険制度により、医療費が一律かつ低コストで提供されています。診療報酬は細かく定められており、医療機関の自由度は非常に低く、経営上のインセンティブも乏しいのが現実です。
さらに、営利企業による病院経営が禁じられているため、アメリカのような“支援で稼ぐ”というモデルはなじみにくい状況にあります。



日本の病院は“患者ファースト”すぎて、ビジネスの話は後回しになりがちっすね…
医療現場の文化と組織的導入障壁
加えて、日本のICUでは主治医制(オープンICU)が主流で、専属の集中治療医が全体を管理するクローズドICUのような体制が確立していません。そのため、遠隔での指示や支援が活かされにくい構造になっています。
さらに、若手スタッフが多くを担う夜間帯に急変が発生しやすく、報告・判断の遅れが問題になっているにもかかわらず、現場に「外から口を出される」ことへの抵抗感も根強いとのこと。
フィリップスはまずは現場の課題を“可視化”し、ワークショップなどを通じて当事者の意識を変えていく取り組みからスタートさせました。これにより、病院側が自ら“必要性”を感じるようになれば、導入も前向きに検討されるようになる──そんな地道な浸透戦略が進められているのです。
おわりに
Tele-ICUという技術は、単なる“遠隔モニタリング”を超え、医療現場における質の向上・効率化・働き方改革といったさまざまな課題に対するソリューションとなり得る存在です。アメリカでは成果主義と制度設計が後押しし、日本では文化的・制度的な壁がある一方で、高齢化という社会的背景がその必要性を高めています。
導入のハードルは依然として高いですが、「医療現場を支える」という純粋な目的に立ち返ると、その価値は計り知れません。



技術の進化が、“人”の負担を減らす。そのための挑戦だな
遠隔医療はあくまで手段であり、目的は“安心して命を預けられる医療”の実現が出来るのか、これからも注目していきたいテーマでした。







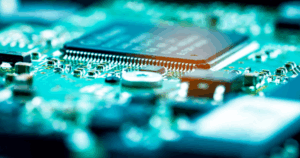


コメント