こんにちは、Yatzです!
今回は 「Patients Like Me」(PLM)です。正直全く知りませんでしたが、なんて良いサービスなんだと、サービスを知って応援したくなりました。
と、ここでは、患者自身がデータを共有することで生まれる価値について、今回も自分自身の備忘録にもなるように整理します。患者コミュニティの広がりとその背景にある技術、そして収益モデルまで、流れに沿ってまとめます。
Patients Like Meについて
PatientsLikeMe(PLM)は、2004年に米国マサチューセッツ州ケンブリッジで、Jamie Heywood、Benjamin Heywood、Jeff Cole によって設立されました 。ALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者だった Stephen Heywood の体験をきっかけに、「患者のリアルな経験」共有の必要性から誕生し、2005年10月にALS患者向けのオンラインコミュニティとしてローンチされました。
その後、2011年に対象をすべての疾患に拡大し、現在は約83万〜85万人以上のユーザーが2,800〜2,900以上の疾患を対象に、自らの症状、治療歴、副作用、生活習慣、気分、QoLなどを継続的に記録・グラフ化して共有しています 。ユーザーによって生成されたデータポイントは4,300万件以上にのぼり、臨床研究や製薬企業との共同研究に活用されています。
PLM は広告料に依存せず、臨床試験設計やPRO(患者報告アウトカム)開発支援、治療アドヒアランス調査などの研究サービスを提供することで収益を得ています。また、100本以上の査読付き医学論文を共同出版し、学術的な信頼性とエビデンス構築にも貢献しています。
創設から約20年以上(2025年時点)を経て、PLMは患者主導のリアルワールドデータ共有を軸としたプラットフォーム構築に成功し、医療研究とビジネスをつなぐ橋渡しとして成長しています。
ユーザー主導のヘルスデータ共有がもたらす価値
病気と闘う人々がつながる「PatientsLikeMe」のサービスとは
PLMの最も画期的な点は、点在する希少疾患の患者同士が“自分の言葉”で経験を共有できるようにしたことです。多くの希少疾患では、標準治療が存在しなかったり、エビデンスが乏しく、患者本人や家族は情報の海の中で孤立しがちです。
PLMでは、症状や治療履歴、副作用、気分、日常生活の工夫などを可視化し、同じ疾患を持つ他のユーザーと比較・参照することで、実践的な知恵や安心感が得られる設計となっています。これは「医師の説明だけでは得られない情報」を補完する役割を果たしており、特に孤立しがちな希少疾患患者にとっては人生の羅針盤的な存在になりうるのです。
 シバキチ顧問
シバキチ顧問一人じゃなくなることが、治療の第一歩かもしれんなぁ。
患者コミュニティの輪と参加者の多様性
現在PLMには、2,800〜2,900を超える疾患がカバーされており、その多くは「情報が足りない」「医師に聞いても具体的な生活のアドバイスがもらえない」といった悩みを抱える疾患群です。特に希少疾患では、地域に専門医がいないケースも多く、患者は「ネットで調べるしかない」という状況に置かれがちです。
そんな中でPLMのようなサービスは、「どこかに似た境遇の人がいて、自分と同じ悩みに対処している」という事実に気づける、貴重なコミュニティ空間です。匿名ながらも正直な声が集まることで、「こうしたら良かった」「これは悪化した」など、生活のリアルなヒントが得られます。



僕も入社したてで右も左もわからない時、先輩の実体験が一番助かりました!
医療業界における立ち位置と競合との違い
多くの医療系SNSやQ&Aサイトは、医師からの回答を中心に構成されていますが、PLMは真逆の発想です。「答えを持たない医療」に対して、集合知で道を探す」という思想で、患者同士の情報交換に重きを置いています。
この点が、例えば医療監修が中心の掲示板や、専門医に相談するだけのサービスとは決定的に異なります。PLMは、希少疾患など「医療サイドに答えがない」領域こそ、その強みが際立つのです。



なぁネコマタ、医者が“わからん”時に誰が助けてくれるかわかるか?



…たぶん、同じ病気の人ですよね



そうだ。その声を集めたのがPLMだ
医療ビッグデータ活用を可能にした技術基盤
希少疾患患者の情報は、どうしても「点」としてバラバラに存在してしまいます。それを「線」や「面」に変えるのが、PLMの技術基盤とユーザーインターフェースです。
ユーザーの体験を定量的に記録・可視化するこの仕組みは、特に症例数が少ない疾患において「再現性あるナレッジの集積」につながりやすくなっています。臨床試験すら実施が難しい希少疾患領域で、このようなデータは貴重な研究資源です。
成功の鍵となるネットワーク効果
PLMの真価は「数の力」がもたらす安心と発見です。希少疾患であっても、世界中の患者が少しずつ経験を共有すれば、やがてその積み重ねが治療指針や生活改善のヒントになります。特に「自分一人では気づかなかった症状の前兆」や「意外な副作用の傾向」などは、PLMのようなコミュニティ型のネットワークだからこそ見えてくるものです。
これは、情報の「集約」と「再利用」が自然に発生するネットワーク効果の好例であり、患者間の自発的な協力が、希少疾患という難しいテーマにおいても突破口となることを証明しています。
「患者の声」を収益につなげるモデル
PLMでは、患者から得られる日々のリアルな声=未整理の貴重なエビデンスを、企業側にとって意味のある形に加工・活用しています。製薬企業にとっては、特に希少疾患においては「患者数が少なすぎて何を調べたらいいかわからない」状況であり、PLMのデータは「実際に困っている人たちの本音」を把握するための指針になります。
言い換えれば、「答えのない医療課題」に対して、「現場から集めた問いの束」でアプローチしているのがPLMなのです。
さいごに 希少疾患の“点”を“線”につなぐ、患者視点のイノベーション
PatientsLikeMeは、2004‑05年創業以来20年以上にわたって進化し続けてきた、患者主導のデータ共有型プラットフォームです。
累計数十万人の患者が、患者同士が経験を共有することで、これまで点在していた情報を線にし、さらには面へと広げていく力を持ったサービスです。特に希少疾患領域では、その価値がより際立ちます。医療情報が不十分な中でも、患者自身の声が集まることで“生きたエビデンス”となり、他の患者の生活の指針にもなります。
将来的には、対象疾患のさらなる拡大に加え、AI・オミクスとの連携強化、そしてプライバシー保護と信頼の両立という課題への対応が、PLMの次なる進化の鍵になりますが、
これからの医療において「情報は医師からだけ得るもの」という固定観念が薄れつつある今、PLMのような「患者の声が主役になる仕組み」が、今後ますます求められていくと実感しました。




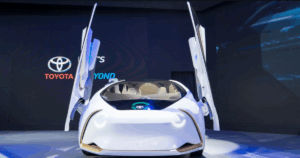



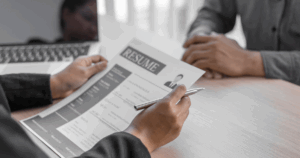

コメント