こんにちは、Yatzです!
今回は、誰もが知っている「松下電器」。
いまでは「パナソニック」としておなじみですが、90年代から2000年代初頭にかけては、あの松下ですら経営の荒波にもまれてました。特にMCA買収や3DOリアルの失敗は、「なぜ、あの大企業が…?」とツッコミたくなる場面が盛りだくさんです。
今回は、そのドタバタ劇を備忘録的に振り返りながら、経営判断や組織のあり方、そして中村改革がどう機能したのかを備忘的にまとめてみたいと思います。
ケース要約
1990年、松下電器はアメリカの大手エンタメ企業MCAを約7800億円で買収。当時は「マルチメディア時代の到来」が叫ばれており、映像・音楽といったソフト資産を手に入れる狙いとしては理にかなっていました。
けれど、買収後は協業体制の構築に1年以上を要し、その間にナショナルリース問題や冷蔵庫の品質不良といったトラブルが続出。社内は火消しに追われ、MCAとの関係構築どころではなくなってしまったんですね。
加えて、当時の谷井社長と松下会長の対立、つまり“創業家の影”も重なって、意思決定のスピードも方向性もバラバラ。1995年にはMCA株の大半をカナダのシーグラム社へ売却する事態となります。
また同時期に進められた「3DOリアル」は、“未来のマルチメディア端末”として意気込んで投入されたものの、価格設定やソフト開発支援策の失敗により市場に受け入れられず、最終的には97年に撤退。
この間、事業部制の限界、派閥争い、「本社病」とも呼ばれる硬直した組織文化が深刻化。1991年・1997年に組織改革を試みるも効果は限定的でした。
そこに現れたのが、2000年就任の中村邦夫社長。彼は従来の成功体験を「過去の遺産」と断じ、徹底的な改革に着手。2001年には「創生21」を打ち出し、事業部制の解体、マーケティング本部の新設、販社の統合、年金制度の見直しなど、“聖域なき改革”を断行していきます。
松下電産の失敗が示す経営意思決定の限界
MCA買収:ビジョンは正しくても、体制がボロボロ
MCA買収の狙い自体は間違ってなかったんです。ソフト資産を押さえるという意味では、むしろ時代を先取りした挑戦でした。
問題は、社内の体制が伴っていなかったこと。協業委員会が発足するのに1年以上かかるなんて、買収後の動きとしては致命的。
さらに、社長と会長の間で方針が割れたことで、組織としての意思統一も不十分。「誰が責任を取るのか分からん」まま、現場は混乱していくばかりでした。
 シバ部長
シバ部長勝負のタイミングはよかったけど、準備が出来てない以上勝てるものも勝てないですね…
3DOリアル:ハード偏重とソフト軽視の代償
「3DOリアル」はゲームも音楽も学習もできる“夢の機械”として登場したんですが、初値が7万9800円という高価格。ソフトはイマイチで、消費者の期待とはズレてました。
さらに、ソフト開発支援策もズレてて、「松下が出資してくれるから…」というだけで売れそうにないソフトが乱立。結局、ハード偏重の思想が仇になり、任天堂やソニーに完敗。



メーカーにとっては金だけ出す都合の良い松下と舐められてるうちは、ソフトの重要性を知っている競合企業には勝てんわな。
事業部制の限界:「トップ案件」にせず、現場完結できていれば…
MCAも3DOも、どちらも社長直属の“特命案件”として進められ、現場の裁量が乏しかった。実態はトップ主導で、現場が自律的に動ける環境ではなかったんです。
この教訓は、「戦略が正しくても、組織体制がそれに追いかないと意味がない」ということを物語っています。
官僚主義と派閥構造がもたらした「スピードの欠如」
事業部制の罠:「縦割り」がイノベーションを殺す
松下電器が失速していった要因は、単なる経営判断ミスや技術の遅れではありません。もっと根深い問題――それが、組織構造と文化の硬直化でした。
とくに事業部制は、部分最適に走りやすく、技術・営業・企画などの連携もスムーズにいかない。社内で名刺交換が必要になるほど、縦割りが強固だったというのは象徴的な話です。



えっ!同じ会社の人なのに名刺交換するんですか!?
派閥も深刻でした。トップが代わるたびに方針が変わり、「谷井派」「森下派」といった対立構造が組織全体のエネルギーを削いでいきました。
創業家の影:「誰が責任とるねん問題」
さらに、創業家――つまり松下家の影響力が意思決定に影を落としていました。社長と会長の間で判断が割れ、現場はその都度振り回される。谷井氏が創業家からの独立を図ったものの、結果的には退任という形に。
こうした空気は、「誰も本気で責任を取らない」構造を生み出し、組織のスピードを著しく低下させる原因となっていたんです。
中村改革が目指した“破壊と創造”の全貌
CSプロジェクト:事業部制の“破壊”から始まる
2000年、社長に就任した中村邦夫氏は、従来の成功体験にとらわれない「破壊と創造」を掲げ、改革の舵を取りました。
その象徴が「CSプロジェクト」。一見“Customer Satisfaction”の略にも見えるこの改革は、実態としては「事業部制の解体」でした。営業・宣伝・商品企画・価格決定などの機能を集約し、「マーケットイン」の体制を整えます。



急に部署がなくなるんですか?わたしの部署がなくなったらどうしよう。
構造改革:聖域なき再編がはじまる
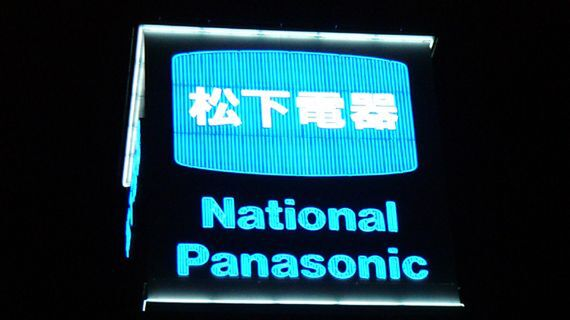
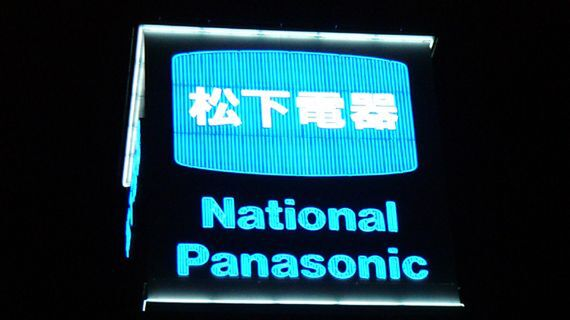
† 出典元:ASCII.jp記事
中村改革では、組織・制度・働き方のあらゆる部分に手が入りました。主な取り組みは以下の通りです:
- 本社スリム化:1300人→500人に縮小、組織もフラット化
- EMS導入・SCM整備:週単位の納品が可能な生産・物流体制へ
- 販社の統合:全国にあった販社を統合し、1万7000店舗を再編
- 年金改革:福祉年金の見直しを断行、「私利私欲で言うな」と言い切る姿勢
- グループ再編:松下通信などグループ5社を完全子会社化
- R&D再構築:技術のブラックボックス化で競争力を強化
そして、「門真から離れるほど元気になる」という声に着目し、地方・海外への権限委譲も進めていきます。これは、“本社病”からの脱却を図る意図もあったのでしょう。
さいごに 〜過去にすがるな、未来をつかめ〜
MCAや3DOの失敗は、単なる「過去の黒歴史」ではありません。
そこには、どれだけの規模と技術を持った企業でも、組織が硬直すれば失敗するという、普遍的な教訓があります。
他のテーマ(IBM)でもありましたね。デカくなり過ぎるのも問題ですね。
中村改革は、その“負の遺産”を自らの手で断ち切り、次の時代へ会社をつなぐ挑戦でした。最終的に2008年、「パナソニック」への社名変更は、まさにその象徴でもあります。



名刺に“松下電器”って書いてた時代が懐かしいわ…でも変わることを恐れたら、置いてかれる時代だな
自分の働く組織や、自分自身の仕事のスタイルに照らしても、この一連のケースは多くの示唆を与えてくれるように思います。








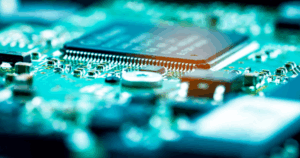

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 松下電器産業 2000 中村改革 […]