Day4の備忘メモ
ナイキ
- 実験を恐れない
- バズりを最も理解している企業
- モノ売りでなく体験提供
- 「対話と共感が重要」であり、「参加」「共感」「関係性」こそがブランドの鍵になる
ハイラックス時計
- 広告の手順(フレームワーク)
①広告目標の設定
・どの程度の、どのようなターゲットに対して、
・「情報を提供したいのか」「説得したいのか」「思い出してほしいのか」を特定
②広告予算の設定
③メッセージ開発
代理店任せにしない。骨子は決めた上で指示
④媒体選択
⑤広告効果の測定と評価 - 広告実施時の鉄則→ 『継続』すること!
サムスン
- 均質な研修モデルでは、多様な背景を持つ人材に響きにくくなっている
- 序列主義から、個人の尊重・平等志向へと急速に変化
- インナーコミュニケーションは、一方的な“お知らせ”ではなく、対話・共感・翻訳(リフレーミング)
ナイキ ソーシャルメディア戦略
1970年代~2012年のお話です。またまた、ナイキさんですね。
ナイキは1970年代にランニングシューズの革新によって市場を拡大し、1980年代~90年代にかけて「Just Do It」などの広告キャンペーンでブランド認知を高めました。その後、2004年からソーシャルメディアへの取り組みを始め、Nike+やFuelBandといった「製品+体験」の提供を通じて、デジタル空間とリアルのスポーツ体験を融合し、ユーザーのデータを活用し、個々のアスリートと継続的な関係を構築してきております。
ナイキはなぜ「モノ売り」から「体験提供」に進化できたのか?実験から始まったブランド戦略の転換が読み取れるケースでした。
1970年代~1990年代のナイキのマーケティング・コミュニケーション
ナイキのマーケティング戦略の歴史を振り返るなら、まず触れておきたいのが1970年代の“原点”。
この時期、ナイキはランニングシューズ市場で一気に存在感を高めます。
革命の始まり「ワッフルソール」
当時のスポーツシューズ業界において、ナイキのワッフルソールは革新的でした。

ワッフルソールとは?
ナイキの共同創業者ビル・バウワーマンが1971年に開発。ゴム製アウトソールに格子状の突起を持たせることで、従来よりも圧倒的にグリップ力と軽量性を両立させた技術。
朝食用のワッフルメーカーにゴムを流し込んで試作した、家庭実験から生まれました。
「発明って、ほんま何がきっかけになるかわからんもんやな…。それにしても、ナイキさんのキーワードは実験やで。」
スターと共に歩んだ1980年代
1980年代に入ると、ナイキはさらに象徴的な広告戦略へと踏み出します。
- トップアスリートの象徴としてマイケル・ジョーダンを起用
- 「Just Do It」というスローガンでシンプルかつ強烈なメッセージを打ち出す
- TV・雑誌などマスメディアを通じた一方向的なブランディング
この時代のナイキは、「技術 × カリスマ × スローガン」の3点セットで、ブランドを一気に世界中へ拡げていきました。
「ほんま、“ナイキ=憧れのアスリート”って印象が、がっつり定着したのはこの頃やったな」
参考) Air Jordanの衝撃:ジョーダンが“ナイキを救った”話
この時代、ナイキの躍進を語る上で欠かせないのがAir Jordan 1の成功です。
実は、当時のジョーダンはアディダスと契約したがっていて、ナイキは「3番手候補」だったんです。
でもアディダスもコンバースも社内事情や戦略ミスでジョーダンを逃し、結果的にナイキが契約に成功。
「これ、他のブランドからしたら“めっちゃもったいないことしてもうた…”って今でも悔やんでるやろなあ」
「NBAが禁止したシューズ」=最強のバズ戦略
そして有名なエピソードがこちら。
Air Jordan 1はNBAのドレスコードに違反(黒×赤)していたため、ジョーダンが履くたびに1回5,000ドルの罰金が課されることに。でもナイキはそれを逆手に取り、「NBAが履くなと言ったシューズ」という広告キャンペーンを展開。
これが爆発的に話題となり、若者の心をガッチリ掴んだんです。
「やるやんナイキ、ようこんな逆境を“ウリ”にできたなあ!」
ちなみに、この罰金はもちろんナイキが全額肩代わりしていたそうです。
この時代のマーケティング・コミュニケーションの本質
まとめると、ナイキの1970〜1990年代の戦略は以下のように言い表せます。
- 技術的革新(ワッフルソール)と象徴的アスリート(ジョーダン)を掛け合わせ、ブランドアイデンティティを構築
- 「Just Do It」「Air Jordan」など、スローガンと商品を結びつける一貫した世界観を発信
- 一方向的なマス広告で知覚と憧れを作り上げる“王道型ブランディング”
マス向けの王道的なマーケティング手法を取っていますね。今でこそ当然ですが、時代を考えるとマーケティングのお手本のようなものですね。そりゃ急拡大するのも頷けます。
ナイキのソーシャルメディア戦略とマーケティングのパラダイム転換(2000年代以降)
デジタルとリアルの融合──ナイキが仕掛けた実験の数々
2004年以降、ナイキは従来のテレビCMや紙媒体中心の広告手法から一歩踏み出し、デジタルとリアルを組み合わせた新しい形のマーケティングを模索しはじめます。
- 2004年「アート・オブ・スピード」:ブログと短編映画でユーザー参加型のプロジェクトをテスト
- 2005年「タッチ・オブ・ゴールド」:YouTubeでバイラル動画(2000万再生!)を成功させる
- 2006年「Joga.com」:Googleと組んでサッカー特化型SNSを展開し、100万人以上が参加
「こうした初期の取り組みは、時代をちょっと先取りしてて、“ほんまにうまくいくんか?”って空気もあったけど、そこをあえて突っ込んでいった感じやったんよな」
Nike+登場。「モノ売り」から「体験提供」への転換点
2006年、Appleとの提携により生まれたNike+が、この流れを一気に現実のものにします。
センサー付きのランニングシューズとiPodを連動させ、走行距離やカロリーを計測して、SNS上で友人と共有するという画期的な仕組み。
「これは“靴を売る”って話ちゃうねん。ランニングそのものを“楽しく続けたくなる体験”に変えてもうたんよ」
以降、FuelBand(2012)、Nike+ Training、Basketballといったシリーズが次々と展開され、ナイキは「製品+体験+コミュニティ」の三位一体構造を確立していきました。
広告から“共創・対話”の時代へ
Nike+は、「ユーザーが能動的に関わる」マーケティングの道を切り開きました。2010年のW杯キャンペーン「未来をかきかえろ」では、Facebookを中心に動画を展開。
また、SNSで自分のプレー動画を拡散してスターを目指す「ザ・チャンス」も実施されました。
「せやから、これってもう、“企業が広告うって買ってもらう”時代とちゃうわけやな。ユーザーが関わって、参加して、広めてくれる世界観になってきたんや」
これは言い換えれば、Push型の広告からPull型の関係性マーケティングへの移行です。
2010年、ナイキ・デジタルスポーツ事業部の設立
こうした取り組みが個別プロジェクトから“仕組み”へと昇華されたのが、2010年のこと。
ナイキは「ナイキ・デジタルスポーツ事業部」を設立し、「全スポーツにおいて、個人のパフォーマンスを記録・共有し、習慣化する」ためのプロダクトとプラットフォーム作りを推進。
「Nike+の成功が、“なんかエエことやってんな〜”レベルやなくて、“会社の核になる取り組みや!”ってなったんやろな」
この戦略により、ナイキはユーザーの行動データを起点に、商品開発やブランディングに活かすサイクルを手に入れました。
まとめ:実験からエコシステムへ
ナイキの戦略は、最初から完成されたものではなく、むしろ2004年以降の小さなソーシャル実験を通して、2006年には製品+体験の融合へと踏み込み、そして2010年以降、それを企業全体の戦略・組織レベルにまで昇華させていったのかと思っています。
この流れはまさに、
- 「PushからPullへ」(一方通行の広告から、ユーザーとの関係づくりへ)
- 「モノからコトへ」(製品から体験へ)
- 「広告から共創へ」(伝えるから、一緒につくるへ)
という、マーケティングの大きなパラダイム転換そのもの。
未来のブランドの在り方を考える探求心と実験を恐れないカルチャーを強く感じました。
そして、ナイキには「バズる」「バズらせる」重要性を、少なくとも2つの事例について身をもって知っていることがよりマーケティングコミュニケーションの探求に進ませたのかと考えています。
一つは、“バズらせた”成功体験(Air Jordan 1)で、
もう一つは、 “バズらされて苦しんだ”失敗体験(労働環境問題)です。
この体験はナイキに「対話と共感が重要」であり、いかに「参加」「共感」「関係性」こそがブランドの鍵になるのかを、身をもって理解したのだと、私は感じています。
そんな気づきをくれたナイキの変遷は、ビジネスパーソンにとってめちゃくちゃ学びの多いケースだとおもいました。
ハイラックス時計
これはお題が与えられて自由演技で発表するというスタイルでした。
ハイラックス時計は、デザイン性の高いカジュアル腕時計を扱うメーカーで、40代男性を中心にセレクトショップ経由で販売している。自社サイトのみで情報発信していたため、ブランド力が弱く、卸値交渉でも劣勢だった。そこで広告展開を検討。限られた予算の中でラジオ広告か雑誌広告のいずれかを選ぶ必要がある。広告の効果を最大化するには自社サイトとの連携も考慮する必要がある。どちらを選ぶとのお題でした。
広告の手順 ※ネタバレ要素あり
- ①広告目標の設定
・どの程度の、どのようなターゲットに対して、
・「情報を提供したいのか」「説得したいのか」「思い出してほしいのか」を特定 - ②広告予算の設定
- ③メッセージ開発
代理店任せにしない。骨子は決めた上で指示 - ④媒体選択
- ⑤広告効果の測定と評価
そして、広告を実施する場合はとにかく継続する!
課題については、このフレームワークで作成すると良いかと思います。という、フレームワークをGet!できたことが収穫でした。
サムスン 「ひとつのサムスン」スピリット
ナイキに続いて、この授業で2回目の登場です。サムスン。
このケースのテーマはインナーコミュニケーションの重要性となっており、ざっくりいうと、新入社員に対して従来と同じ研修を一律実施することの妥当性が問われ、今後のインナーコミュニケーション戦略をどう再設計すべきかが焦点となっている内容となっています。
ケースの内容 「ひとつのサムスン」スピリット継続に向けて
背景と目的
韓国の経済成長とともに発展してきたサムスンは、創業者・李秉喆(イ・ビョンチョル)の掲げた「事業報国」「人材第一」「合理追求」という三大理念を軸に、人材重視の企業文化を築き上げてきた。1990年代には「ひとつのサムスン(One Samsung)」という統合コンセプトを打ち出し、多様な事業部門や国籍の異なる社員を価値観で一体化することを目指した。これにより、グローバル競争力と内部結束力を両立してきた。
サムスンの企業理念・価値観とその伝達
企業理念は、社員の士気と連帯感の原動力であり、特に以下の5つの価値観が浸透していた:
- 人材第一(企業は人なり)
- 最高指向(常に世界一を目指す)
- 変化先導(革新を恐れず主導する)
- 正道経営(倫理的な判断と行動)
- 相生追求(地域・社会との共存共栄)
この価値観は、主に人材育成機関SHRDCを中心に設計された研修制度を通じて社員へ伝えられた。特に新人研修(NEO)は「サムスン人」になるための通過儀礼とされ、創業者の思想や企業文化、問題解決能力を徹底的に植え付ける場となっていた。
事業展開と組織構築への影響
「ひとつのサムスン」スピリットの下、部門間の協力体制や技術と経営の統合的意思決定が強化され、各社員が使命感をもって行動する自律性と忠誠の両立が実現されていた。また、従来の縁故主義を廃し、成果・実力に基づく人事制度を業界に先駆けて導入。グローバルな採用・育成体制を整え、世界で最も賞賛される企業の1つへと成長した。
現在の課題:多様化・世代間ギャップと「インナーコミュニケーション」の再構築
しかし2008年以降、採用の多様化(経験者・外国人社員の増加)や、デジタル世代の価値観の変化により、旧来の「一体化・集団主義」型の理念・研修モデルに限界が見え始める。若年層は「自律性」や「ワークライフバランス」「オープンな対話」を重視し、企業側も価値観や研修手法の再定義を迫られている。
組織の構築や事業展開に企業理念や価値観のもたらす影響
内容を見ると、サムスンの企業理念は単なるスローガンにとどまらず、極めてシビアかつ合理的な人材育成の方針と結びついており、「人を育てることを通じて、最終的には国家や社会に報いる」という強い意思が明確に伝わってきます。
実際、こうした理念や価値観は、サムスンの組織に求心力・柔軟性・革新性をもたらし、世界トップクラスの企業へと成長を遂げる上で大きな原動力となったことは間違いありません。
特に、サムスン人力開発院(SHRDC)の果たす役割は非常に大きく、単なる人材教育機関を超えて、企業文化そのものを内面化・継承させるための戦略的拠点として機能してきています。SVP(価値共有)、SLP(リーダー養成)、SGP(グローバル能力強化)の3本柱による育成体系は、単にスキル習得にとどまらず、社員一人ひとりにサムスン的価値観を深く根付かせ、価値観を通じた組織的連帯を可能にしています。
また、事業の多角化やグローバル化が進む中で、異なる国・部門・文化背景を持つ社員を一つにまとめ上げるうえで、企業理念とそれに基づく教育体系が「精神的なインフラ」として機能した点も見逃せません。
このように、理念と価値観を軸に据えた組織設計と人材戦略が、変化の激しい環境下における一貫性と競争優位性を支えてきたと評価できます。
再設計する必要ある?
本当にZ世代は、、、と思うことあります。新卒の方と会話する機会が割とありまして、結論「面倒」なやつが多いです。※全員がというわけではないですが、確率としては多い気がします。
どんな面倒かというと、「屁理屈ばかりこねやがる。」です。それ以上はやめときます(笑)
さて、内容に戻ると、サムスンが誇ってきた「ひとつのサムスン」スピリットは、理念や価値観の共有によって社員を統合し、組織の競争力を支えてきました。しかしその前提が大きく揺らいでいる状況です。
まず、新入社員の構成が大きく変化しており、2008年以降、経験者採用が50%増加し、外国人採用も34%増加。従来のような韓国の新卒学生を対象とした均質な研修モデルでは、多様な背景を持つ人材に響きにくくなっているのが実情です。
また、若い社員からは「企業風土が保守的すぎる」「もっとオープンでフラットな関係が望ましい」といった声も出ており、仕事とプライベートの両立を求め、残業や週末出勤を避けたいという考え方も顕著になっており、これは従来の滅私奉公・忠誠重視の価値観とは明らかに異なります。
このように、ベテラン世代とデジタル世代との間に価値観ギャップが拡大しており、場合によっては「すぐ辞めてしまう」といった離職リスクも増しています。「ひとつのサムスン」を掲げているにもかかわらず、実態としては“一つになれていない”という危機が浮き彫りになっているのです。
では、サムスンにとって「便利な人材」とは何か。それは単に指示に従う存在ではなく、理念や文化を理解し、内発的に動ける存在であるべきです。しかし、現状のインナーコミュニケーションでは、そうした人材の「心を掴む」機能が十分に果たされているとは言いがたいということなんでしょうね。
さらに、韓国社会全体も儒教的な序列主義から、個人の尊重・平等志向へと急速に変化しています。この変化に企業が対応できなければ、かつてのように人材を引き寄せ、育成し、組織を一体化することは難しくなっていくでしょう。
したがって、今こそサムスンはインナーコミュニケーションの再設計に本気で取り組むべき時期に来ていると考えます。単なる情報伝達ではなく、「共感」と「対話」を基盤とする新しいコミュニケーション設計が、「ひとつのサムスン」を真に実現する鍵となるはずです。
では、具体的にという話になりますよね。以下は、案となります。
分化と統合の並列
研修を対象別に分化することや、共通項目のパートや個別適応パートに分ける、年次で塊を作るなどのアイデアがありそうです。
聴く文化の導入
若手が悪者ではなく、経験者たちが若手をもっと理解する機会を設けても良いでしょということで、対話をするイベントやSlackや社内イントラをカジュアル化してコミュニケーションを取れる仕組みを入れる
今の言葉で価値観の再文脈化
若手も理解できるワードに変換。一番は顧客のベネフィットが理解できるワーディングが望ましい気がします。あとは、単語じゃなくそれが具体的にどういう行動を指すのかプチドラマなどで視覚化するのもありかもしれないですね。
さいごに 新卒から学ぶこともあるんですね
ここまでケースで扱うと何か親近感持っちゃいますね。サムスン。
とても良い企業だし、以下にも韓国企業という感じがします。
さて、ケースを読むと、上手くいっているように見える企業でも時代の変化に対応しないといけないし、過去の成功体験に安住出来ないのだと感じますね。
顧客に対してもそうでしたが、従業員に対してもかつては、価値観を一方向的に“教え込む”ことで統一感を出すことができた時代もあったのは確かですが、今は“納得してもらう”ことや“参加してもらう”ことがなければ、理念や文化は機能しないんですね。特にZ世代のように「自分の言葉で解釈したい」という価値観を持つ人たちには一方的に“与えられるもの”ではなく、“共につくっていくもの”であるべきなんでしょうかね。
インナーコミュニケーションは、ただの“社内のお知らせ”ではなく、対話・共感・翻訳(リフレーミング)の3点セットで作っていく必要があるんですね。
なんか、新卒も顧客みたいになってきて、管理職としては先輩や上司にペコペコして、今度は新卒にも。めんどくせぇなと思ったら、、、負けなんだろうな。




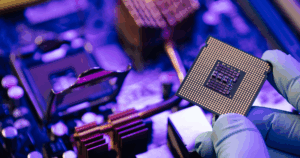
コメント