備忘メモ
ロレアル
- MCの5つのポイント:アイデンティティ・知覚・長期目線と一貫性・接点と整合性・想定内
- 勝負に出るためには「膨大な」広告費用は当然出すくらい腹くくれ
- ロレアルのケースはMCの基本を学べる
コルゲート vs P&G
- 値付けが秀逸 40ドルvs15ドル
- 夜用バージョンで目線そらし(vsエビデンス)
- 自社の強みを誰に、どのように届けるかを設計すること
- 利便性vs技術優位性 体感効果をどのように作るのか
ダイソン
- ダイソンという特別なカテゴリー構築
- 秀逸なメッセージ「ダイソン。吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機」
- ゴミをみせて、掃除を楽しい体験にした
- 関係ない質問を踏まえて使用コンテクストや潜在ニーズの把握
- テクノロージープッシュの良さ
ロレアル 世界最大の化粧品企業のブランド・マネジメント
授業一発目はロレアルです。ケースをもとにロレアルがどのような「マーケティング・コミュニケーション」を行っているのかを考えました。
ロレアルは1909年創業のフランス発・世界最大級の化粧品会社です。メイベリン、ランコム、キールズなど多彩なブランドを展開し、日用品から高級品まで幅広く対応。研究開発力と革新性を強みとし、現在150カ国以上で事業を展開。サステナビリティや多様性にも注力しています。
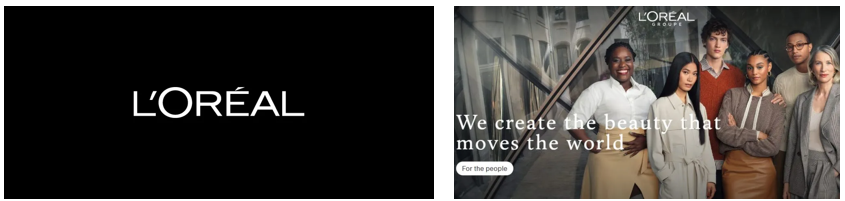
ケースの要約
ロレアルは1964年に高級香水ブランド「ランコム」を買収し「フランスで最大の化粧品ブランドに育てる」という目標を掲げた。買収当初のランコムは、製品ラインの乱立と収益性の悪化に直面しており、ロレアルはまず、ブランド・アイデンティティの確立(象徴的な「バラ」のシンボル、広告やパッケージの統一)と製品ラインの再編成から着手し、ブランド構造を整理・再構築した。加えて、従来の香水・高級品専門チャネルを活用しつつ、マス向けのプロモーション(ラジオ広告、女性誌広告)を組み合わせたことで、高級感と大衆性を両立させるマーケティングを実現。さらに、「スタープロダクト戦略」として、機能性と話題性を備えた製品(例:「朝の恵み」クリーム、後年の「ケラシル」マスカラ)を中心に販促を展開した。
米国市場進出では、広大な市場での百貨店チャネルへのアクセスを得るため、プル型のマーケティング(広告主導型)への転換が必須となった。エスティローダーとの競争下で、差別化された製品開発と強力な広告展開(特に雑誌)を通じてブランド認知を図った。これにより、「高機能×エレガントなイメージ」を打ち出し、米市場に適応していった。
日本市場では、まず美容院チャネルを通じたヘアケア製品展開からスタートし、1978年にランコムが百貨店チャネルで独自に展開を開始。コーセーとの提携を経て独自チャネルを構築し、伊勢丹新宿・阪急梅田など影響力の高い核店舗に集中的に出店。さらにメディア関係者との継続的な関係構築により、認知を高めていった。
1990年代にはマスカラ「ケラシル」のヒットをきっかけにブランドイメージを若返らせ、軽量・高利益のマスカラを軸にした商品戦略を確立。その後もスキンケア・美白市場への製品展開を強化し、日本やアジア市場への浸透を進めた。


ロレアルは「ブランド・エレメント(ロゴ、モデル、容器など)」をグローバルに統一しつつ、製品ポートフォリオや販路、価格設定は現地ニーズに応じて柔軟に対応する「グローカル戦略」を徹底し、世界最大の化粧品ブランドグループへと成長した。
ランコムを買収時(1964年)の戦略
授業でポイントとしてあげられた5つ(アイデンティティ・知覚・長期目線と一貫性・接点と整合性・想定内)をフレームワークとして活用してみます。
※モリアーティの7原則なるものもありますが、7つより5つが覚えられるので
ブランドアイデンティティとして「バラのシンボル」を確立したことが大きかったですね。パット見て分かるというのは素晴らしい。また、長期目線で製品ラインの絞り込みと中核商品の育成もイメージされており、また、高級イメージを維持しつつ、大衆メディアで広告展開(「朝の恵み」など)していると、接点に対して一貫性を持っているように受けられます。
また、統一されたブランド要素(ロゴ、色、イメージ)により、一貫したブランド認知を形成。
ということで、当時のロレアルさんは、コミュニケーション手法のポイントを抑えているのでGOODですね。
米国において「膨大な広告費用」はなぜ必要?
ロレアルは米国に進出するわけですが、百貨店はて店舗ごとの売上規模が大きくここが攻めどころになります。
ただ、百貨店に商品を置いてもらうには売上の見込みが必要です。そりゃ売れない商品置いたら売り場が無駄になりますから。そのため、ランコムを買いたいと消費者がわざわざ来て買うほどの知名度・人気が必要になり、広告による集客力が重要になるということですね。
ランコムはフランスでは香水店で販売員が直接購買を促すプッシュ型マーケティングが中心でしたが、米国市場進出に当たってはその市場の特性からプル型マーケティングにシフトしたという流れですかね。
あとは、米国という世界最大の市場でブランドイメージをさらに高めるに当たって中途半端なことは出来ないですから。勝負に出るためには「膨大な」広告費用は出さないとと腹くくった感はありますね。
プル型マーケティング
「消費者の側から商品を求めさせる」ことを目的としたマーケティング手法。 これは主に 広告・PR・ブランディングによって認知と関心を高め、購買行動を引き起こす方法です。
日本市場参入時に実施されたマーケティング・コミュニケーションについて
ロレアルがランコムを日本市場に導入した際、既に強固なブランド力と流通網を持つ資生堂などの国内大手ブランドが存在しており、彼らは全国に広がる自社流通網とマスメディアを活用した大規模な広告投資で市場を支配しており、同じアプローチを取ればロレアルはその影に埋もれてしまう恐れがあった。という背景はありそうですね。
なので、 資生堂がテレビCM等を使って大規模に展開していたのに対し、ランコムは百貨店バイヤーや女性誌の編集者など、情報発信の影響力を持つ個人との密なコミュニケーションを図ったことや資生堂が全国展開していたのに対し、ランコムは「核店舗集中戦略」を採用したり、チャネルの独自構築を図ることで高級感を体現したのかなぁと。
日本の百貨店集中は、米国の経験値が活かせることも確信していたのかなぁと感じています。
さいごに
授業でわざわざ扱うくらいですから、ロレアルによるランコムのブランド再構築は、まさにブランド・コミュニケーションの教科書的成功例となり、ケースそのものが参考になりますね。
買収当初のブランドの混乱を、「アイデンティティの明確化」「製品ラインの整理」「スタープロダクトによる話題化」といった基本に忠実な戦略で立て直し、高級感と大衆性の両立という難題を見事に乗り越えたのは、当時まだそこまでマーケティングが体系化されていない中での企業活動とするとトップが相当優秀でしたね。
また、米国市場や日本市場への進出は、「グローバルに統一されたブランド要素」と「ローカルに最適化された製品・流通・接点」の巧みな組み合わせ、すなわち“グローカル戦略”が一貫して存在しています。これはMC5つのポイント(アイデンティティ・知覚・一貫性・接点整合・想定内)にも合致し、世界最大の化粧品ブランドへと成長した現在のロレアルの礎となりました。
市場特性を読み取り、ブランドの「らしさ」を守りながらも、柔軟かつ大胆に手法を変えていく姿勢こそ、グローバルブランドの本質ですね。
コルゲート vs P&G もっと輝く笑顔を人々に
2000年から2003年ごろの出来事を中心に描いたケースになっています。
ケースの要約 「白い歯」をめぐるマーケティング戦争
2000年、P&G(プロクター・アンド・ギャンブル)がアメリカ市場に投入した「クレスト・ホワイトストリップス」(約40㌦)は、オーラルケア業界に大きな衝撃を与えました。これは、過酸化水素を含むジェルをストリップ状のフィルムに塗布し、30分間歯に貼るだけでホワイトニング効果が得られるという、当時としては革新的な製品。高価な歯科治療に代わり、自宅で簡単に歯を白くできるという手軽さと効果の高さが評価され、初年度に2億ドルの売上を記録するほどの大ヒットとなりました。
P&Gはこの製品を「ホワイトニング市場」という新たなカテゴリーとして打ち出し、従来の歯磨き剤や歯ブラシが中心だった成熟市場に、美容志向の高い新たな消費者層を呼び込みました。
一方、この分野で長年トップブランドだったコルゲート・パルモリーブは大きな危機感を抱きます。ホワイトストリップスは複数の特許で保護され、模倣が難しい上、P&Gは「従来製品の10倍の効果」と大々的に訴求していたからです。
しかしコルゲートは、技術で勝負するのではなく、「価格」と「使いやすさ」で勝負に出ます。2002年に発売した「シンプリーホワイト」は、歯にジェルを塗るだけという簡便さと、15ドルという手頃な価格で、たった1か月で市場の約半分を獲得。P&Gのシェアは80%超から37%にまで急落しました。
P&G側は、科学的なデータに基づき、シンプリーホワイトの効果は短時間で失われると警鐘を鳴らしていましたが、消費者の多くは「効果を感じた」と満足しており、「科学的根拠」と「体感的な納得感」のギャップが、マーケティング上の課題となりました。
その後もコルゲートはナイト用製品を追加し、「手軽に白い歯を手に入れる」という利便性をさらに強化。一方のP&Gは、比較広告や価格戦略、さらには法的手段まで含めて巻き返しを図ります。
このケースは単なる製品競争ではなく、
- 技術的優位性 vs. 消費者の利便性
- 実証データ vs. 感覚的満足
- 特許による防御 vs. マーケティングによる攻勢
といったマーケティングの本質的な対立軸を浮き彫りにしています。
自社の「強み」をどう伝えるか。競合が予想外の切り口で市場に食い込んできたとき、どう対応するか。今回のケースは、現代のマーケターにとっても非常に示唆に富んだ教訓を与えてくれます。
2000年ごろのオーラル市場
| 項目 | 内容 |
| 市場ニーズ | 歯を白くしたいというニーズは存在していたが、歯科医院でのホワイトニングは高額。 市販の歯磨き剤は効果が薄く、“中間的選択肢”が存在しなかった。 |
| 主要プレイヤー | コルゲートとP&Gが米国市場を支配。ユニリーバなども参入していたがシェアは限定的。 |
| 競争環境 | 米国市場は成熟期で成長停滞(年平均成長率−0.6%)。製品差別化が困難で、ブランド力とマーケティングによる消耗戦が続いていた。 |
この状況下で、P&Gは「クレスト・ホワイトストリップス」発売で、家庭用ホワイトニングという新カテゴリー創出に成功します。
そして、口腔衛生から「美容・見た目重視」への顧客による購買動機のシフトを促しています。
コルゲートの対抗策
ぶっちゃけ、ライバルが市場を作って成長しているのを黙ってみているわけにはいかないですね。
ということで、塗布型ジェルで低価格(15㌦)の「シンプリーホワイト」を発売します。
- P&Gと「同等の効果」にもかかわらず「より簡単で使いやすい」と訴求
- 広告・店頭展開で大量拡販
により発売1ヶ月でシェア50%近くを奪取してしまいます。さらに
- 「夜用バージョン」も投入し、製品バリエーションも追加しています。
これも上手いですね。中身が分からない消費者からしたら、「きっとこの商品は夜用にカスタマイズされているんだ」「寝ているうちに勝手に歯が白くなるように設計されているんだ」なんて勝手に想像しちゃいそうですし。
これ値付けがとにかく秀逸だと思いました。
ライバル40ドルに対して、15ドル。2個買ってもまだおつりが来る。
買う方としては、使い方含め気軽に買えるわけです。
結果として、消費者認知でも、「P&Gと同じ効果・より便利」という結果につながっています。
理屈よりも体験・印象が勝ったということですかね。
さいごに いいモノを作れば売れる、、、わけではない
本ケースでは、「体験的満足感」が「科学的根拠」を凌駕することもあるという事実が描かれていましたね。日常でも体感することでもありますが、消費者は必ずしも理屈で動くわけではなく、直感的な理解や納得感によって購買を決めていく。この“感覚の論理”を読み解けるかがマーケターの力量です。この点は行動経済学にも当然通じるところがあります。
P&Gとしては、コルゲートのような「価格×利便性」戦略とは正面からぶつかるのではなく、例えば“医師推奨”や“長期的効果”といった専門性の高いメッセージやエビデンスを強化し、「効果の信頼性を重視する層」向けにポジショニングを明確化すべきかもしれませんね。すなわち、市場全体を取りにいくのではなく、「自社が信頼で選ばれるブランド」であることを丁寧に訴求し、市場の棲み分けを通じて中長期的にロイヤルユーザーを確保するという視点です。
「戦い方を選ぶこと」は当然そうですが、「自社の強みを誰に、どのように届けるかを設計すること」と5つのポイントの要素の実現の難しさと可能性、そして“生活者目線”を忘れないことの重要性を教えてくれました。
ダイソン 日本市場への参入
さて、2004年から2005年を中心とした、ダイソンが日本市場に来た時のお話です。
ケースの要約
ダイソン株式会社は、英国発の技術ベンチャーとして誕生し、創業者ジェームズ・ダイソンが開発した「吸引力の変わらない掃除機」で世界的に知られる企業です。紙パック不要のサイクロン技術、高い排気清浄性、そして洗練されたデザイン性を武器に、イギリスや欧州で成功を収めた後、1998年に日本法人を設立。翌1999年から本格的に日本市場へ参入しました。
しかし、いざ日本市場に進出してみると、欧米とは異なる住宅事情や消費者ニーズという壁に直面します。たとえば、収納スペースの狭さや、掃除機に求められる軽量性・静音性など、日本の暮らしには独自の要件があったのです。従来の欧州向けモデルでは、そうした細かなニーズに応えきれませんでした。
そこでダイソンは、本社からエンジニアを来日させ、家庭訪問やフォーカスグループインタビューを通じて徹底的なユーザー調査を実施。日本の消費者が本当に求めているものを、現場で丁寧に拾い上げていきました。
その成果として、2004年に日本専用の小型・軽量モデル「DC12」を開発・発売。このモデルは、ダイソンの代名詞でもある強力な吸引力はそのままに、日本の住宅環境にフィットするサイズと仕様を実現。結果、発売から1年で市場シェアを0.5%から12%へと急拡大させる、大きな成功を収めました。
マーケティング戦略もユニークでした。高価格でも性能を正当に評価する層をターゲットに設定し、「吸引力の変わらない、ただ一つの掃除機」という明快なメッセージを掲げ、テレビCMや新聞・雑誌広告、イベント、交通広告など多彩なメディアを活用。さらに、量販店との関係強化や店舗配荷の拡大にも注力し、販売員による現場での推奨を通じて購買を後押ししました。
こうしてダイソンは、“高価格帯プレミアム掃除機”という独自ポジションを日本市場で確立。その後は、ターゲット層を富裕層や健康志向層から一般家庭へと拡大し、製品カテゴリの多様化やIoTとの連携といった新たな成長戦略が求められるフェーズに入っています。
ダイソンのマーケティングミックス
ダイソンの特徴はやはり、その独自性がそのまま優位性になっている点ですね。
サイクロン技術はもとより、デザイン・エンジニアが一体化した開発体制、そして特許保有数(1,000件以上)
| 4P要素 | 内容 |
| Product | –「吸引力の変わらない掃除機」= サイクロンテクノロジー – 紙パック不要で排気が非常にクリーン – クリアビンにより「可視化された清掃」 |
| Price | プレミアムプライス戦略(他社の2〜3倍の高価格) |
| Place | イギリスを起点に欧州全体・アメリカ市場にも展開。マレーシア工場で一貫生産。 |
| Promotion | 自社でブランド構築。製品自体が強力なメッセージ(=技術・デザイン)。 |
強烈なのが、
「吸引力の変わらない掃除機」
です。わたしも買いましたよ。2004年当時で7万円以上したと思います。
そして、、、後悔しました。
「髪の毛が絡まり易っ! 吸引力弱いっ! 全然紙パック式の方がゴミが取れるやん!!」と。
でもね。ダイソンの上手いところが、
吸引力は弱くても、弱いまま「変わらない」で嘘ついていない。
ゴミはクリアビンで取れた量がハッキリ見えるのでなんかゴミ取れている感をめっちゃ感じるわけです。
デザインも良いので、結局、ゴミ掃除ライフを楽しくさせる的になんかネガティブよりポジティブが世間では勝ったんですね。
日本でのローカライズ
本社技術者が来日し、実地で日本の家庭を訪問し、購買動機、清掃習慣、製品不満点のヒアリングするわけです。
で、
- 日本の家庭は収納スペースが狭く、軽量・コンパクト性が求められる。
- 一般掃除機ユーザーは「吸引力の低下」「目詰まり」に不満。
- アレルギー持ち・子育て世帯は排気の清浄性を重視。
- 高価格だが機能性が高ければ購入意欲あり。
といった情報からDC12を開発するのですが、必ずしも製品とは関係ない質問も含まれていました。
それは、実際の使用コンテキスト(どんな場面で、どんな目的で、誰が使うなど)やターゲット顧客の深層心理や購買動機、代替手段の存在、コミュニケーションチャネル戦略のヒントなど幅広く収集できるものだったのもポイントかと思います。
そして、日本でのマーケティングとして
- ジェームズ・ダイソン本人登場
- 銀座駅構内ジャック・車体広告
- TVCM、新聞(全国紙)、雑誌(見開き広告/アドバトリアル)

と、デザインや高級感を含めた認知拡大に成功するわけです。
特に当時は家電量販店での掃除機売り場では、ダイソンだけ別コーナーとなっていましたね。そして、店員も積極的にダイソンをアピールするわけです。
そりゃ売れる商品は力入れるでしょうし、価格は高いけど他の製品と比べて差別化の説明もし易い。顧客も高いということは良い商品だ!とあらゆる媒体でのマーケティングとあわせて良い流れが出来るわけです。
手金をつぎ込んで、何年もかけて開発と、人生をかけた男の勢いはさすがということであっという間に日本でもシェアを確保するわけです。お見事でした。
さいごに ダイソンの現在位置とこれから
高価格・高性能路線で志向性の高い層から支持を得る一方、中間層には価格と機能のバランスが求められており、リーチには限界も見えます。これからは製品そのものではなく、空気の可視化やアプリ連携といった体験価値の提供が鍵となります。
「高級」ではなく「高満足」へ――長寿命や複合機能を通じて、所有する意味を強化する必要があります。また、吸引・空気制御といったコア技術の水平展開により、空調や医療分野などへの広がりも期待できます。
ダイソンの本質は、生活の不満を起点に、技術で解決策を提示する“テクノロジープッシュ”の姿勢にあります。今後も、先回りして暮らしのスタンダードをつくる存在であり続けると思っています。




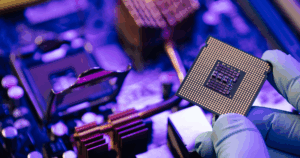
コメント