こんにちは、Yatzです!
ブランド戦略や経営組織の研究対象として、LVMHほど興味深い企業はそう多くないと思います。
1989年、若干40歳でグループの支配権を握ったベルナール・アルノー氏によって、高級ブランドの集合体へと変貌を遂げたLVMH。今回は、その成長過程や戦略のエッセンスを、自分用の備忘録としてまとめておこうと思います。
 ネコマタ商事
ネコマタ商事うーん、こんなブランド集団がどう動いてるのか、気になっちゃいますよね…
LVMHの要約
LVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン(以下LVMH)は、ワイン・スピリッツ、ファッション・レザーグッズ、香水・化粧品、セレクティブ・リテーリングの4部門を持つフランス発の高級ブランドコングロマリットだ。傘下には、ルイ・ヴィトン、クリスチャン・ディオール、ケンゾー、ゲラン、ヘネシー、DFS、セフォラなど、創業100年を超える老舗から戦後生まれの新興企業まで多彩なブランドが名を連ねる。
1989年に会長兼CEOとなったベルナール・アルノー氏は、M&A戦略を武器に次々とブランドを傘下に収め、ブランドの独自性を損なうことなく、グループとしてのシナジーを追求するという独特の戦略を展開していく。
1997年には売上高480億フラン(約1兆800億円)、純利益は48.7億フラン(約1,100億円)を記録。従業員数は、DFSとセフォラの買収により、前年の20,640人から32,350人へと1.5倍に増加した。
売上構成比で見ると、セレクティブ・リテーリングが30%、ワイン・スピリッツとファッション・レザーグッズがそれぞれ25%、香水・化粧品が19%。地域別ではアジア太平洋(日本除く)26%、北米22%、日本14%、フランス13%となっており、日本を含めたアジア市場の存在感は非常に大きい。
また、アルノー氏の掲げた経営理念は5つの価値観から成る:
- 創造性と革新
- 製品の卓越性の追求
- ブランドの確立
- 起業家精神
- 最高を目指すこと
この理念は、アーティストのようなデザイナーたちと、実務を担うマネジャーたちが共存し、互いに刺激し合うLVMHならではの文化を象徴している。
さらに、人的資源戦略としては、世界中からハイポテンシャルな人材を発掘・育成し、300人の幹部と300人の候補生を「Ready to move」リストに乗せて育てている点も特徴的だ。評価制度にはアメリカ式の目標管理(MPP)を導入し、コンピテンシーと業績の両面から人材を磨いていく姿勢が見て取れる。
このように、LVMHは単なるブランドの集合体ではなく、「伝統と革新」「自立と統合」「アートとビジネス」のバランスを巧みに取りながら、ブランド帝国として成長を続けている。
買収によるブランド拡大戦略の進化
ステージごとにみる戦略の変遷と意図
ベルナール・アルノー氏の戦略を一言で表すなら、「攻めのM&A」である。彼の戦略は単なる買収ではなく、LVMHのブランドポートフォリオを高級市場の最上位に位置付ける、いわば“帝国建設”のような意図が見える。
1984年に経営破綻した繊維会社ブサックを買収し、その傘下にあったクリスチャン・ディオールを獲得したことがすべての始まりだった。その後の買収劇は怒涛のように続く。
- 1991年:ポメリー(シャンパン)
- 1993年:KENZO(高田賢三)
- 1994年:ゲラン(香水)
- 1995年:フレッド(宝飾)
- 1996年:ロエベ(スペイン高級皮革)・シャトー・ディケム(ワイン)・DFS(免税店)
- 1997年:セフォラ(化粧品セルフ販売店チェーン)
アルノー氏は、ブランドの拡充とともに“流通”にも注目し、DFSやセフォラといった小売部門の買収を進めている。これは「タテの統合」を狙った動きであり、高級ブランドの販売網まで自社でコントロールすることで、ブランド価値を末端まで維持するという発想だ。



つまり…ブランドだけじゃなくて、売り方まで押さえるってことですね…?
また、DFSの買収により、LVMHの売上は前年比5割増、従業員数も1.5倍へと急増。一方で、この買収直後にアジア通貨危機が起こり、日本人観光客が激減。戦略としてのタイミングにはリスクも伴っていたが、結果的にはアジア市場の長期的成長に繋がる布石となった。
アルノー氏は買収対象の選定基準について、「ブランド価値の維持・強化に寄与するか」「将来性があるか」に重点を置いている。そして、買収後も各ブランドの自立性は尊重し、ファミリー企業的な雰囲気は保たれるよう配慮している。



バラバラなブランドを一つにまとめるって、筋トレしながらパズルするようなもんだな
このように、LVMHのブランド拡大戦略は、財務的なリターンを狙うだけでなく、ブランド同士の“化学反応”を生む土壌づくりでもあったと言える。タテの統合とヨコのシナジー。これがLVMH流のM&A戦略だ。
ブランドビジネスの統合と分権的マネジメント
ブランドアイデンティティを守るための組織設計
LVMHのユニークさは、単なる持株会社で終わらず、“ブランドの個性を生かしたままグループとして統合する”という巧妙な組織運営にある。アルノー氏はこのバランスを、「強いシナジー」と「高度な自立性」で両立させようとしてきた。
具体的には、ブランドごとに経営の自由度を残しながらも、本社では財務・人事・法務・広報・購買といった共通機能を集中管理。傘下ブランドの中には、18世紀創業のモエ・エ・シャンドンやヘネシー、19世紀創業のルイ・ヴィトン、ロエベといった伝統企業も多く、各ブランドの「歴史と文化」は最大限に尊重されている。
一方、買収で傘下に加わったブランドの幹部にとっては、企業文化の違いによるカルチャーショックもあったようだ。だが、LVMH本社はその緩衝材として、社内報の発行、経営幹部会議の開催、人事評価制度の統一などを通じ、グループとしての一体感を丁寧に築いてきた。
また、LVMHは地域ごとに統括拠点を置き、パリ(欧州)、東京(日本)、香港(アジア太平洋)、ニューヨーク(アメリカ)という構造をとっている。ここでは、各地域ごとの調整機能を担う一方、損益責任はブランド単位という“分権型”の経営方針が徹底されている。



一見バラバラに見えるブランドたちが、“緩やかな連邦制”でまとまっている感じかね
重要なのは、中央集権にしすぎると創造性が死に、分権にしすぎると統制が効かなくなる。その絶妙なバランスを、LVMHは「経営理念の共有」と「限定的な集約」で乗り越えているのだ。
アルノー氏の「ブランドアイデンティティを損なうな」という強い意志が、こうした組織構造に色濃く表れている。
成功要因としての人的資源戦略
デザイナーとマネジャーの育成と活用
LVMHの最大の資産は「人材」といっても過言ではない。特にブランドの“顔”となるデザイナーと、それを支えるマネジャーの両輪が、同社の競争力を支えている。
同社では「Management of Performance and Potential(MPP)」という共通の評価制度を導入し、職務目標に基づく業績評価とコンピテンシー評価(専門性、チームワーク、リーダーシップ、柔軟性など)を実施。この制度は世界中の社員に共通で、自己評価→上司評価→フィードバックという流れで実施される。
また、ハイポテンシャル(HP)人材は300人規模で、3年以内にCEOクラスになりうる層や、2職階以上の昇進が見込まれる若手を計画的に育成。さらに「Ready to Move」として、異動・昇進が可能な約100人をストックし、組織横断的な人事配置ができる体制を構築している。



任せること、動かすこと、それが部下のエネルギーを引き出すコツです
プロフェッショナル人材、とくにデザイナーに対しては、通常の人事評価ではなく長期的なインセンティブを重視。ルイ・ヴィトンのマーク・ジェイコブス、ジバンシィのアレクサンダー・マックイーン、ケンゾーのケンゾー・タカダなど、世界各国の一流デザイナーをスカウトしてブランドの刷新を図った。
他にも、香水のブレンダーやテイスター、ファッションのパタンナーなど、職人技とクリエイティビティが融合する専門職を多数抱える構造が、LVMHの多様性を支えている。
現在と将来の課題
ブランド間競合とグローバル市場の変化
LVMHグループ内では、クリスチャン・ディオール、ゲラン、ケンゾー、ジバンシィなどが香水市場で競合し、各社がそれぞれ独自のマーケティングと営業を展開している。これは表面上は非効率にも見えるが、結果的に「内部競争による革新」を促す土壌となっている。
一方、1997年のアジア通貨危機では、主力市場である日本とアジア太平洋地域が大きな影響を受けた。DFSの売上も減少し、観光客依存のモデルの脆弱性も露呈した。
また、グローバルにおけるブランド価値の維持と、各国の文化や市場変化への対応というジレンマも見逃せない課題である。
持続的成長への戦略的対策
新興市場とデジタル時代への適応
LVMHは、アジア新興市場やデジタルシフトへの対応も積極的だ。セフォラのようなセルフ販売店の導入や、新しいブランド流通網の構築により、Z世代を含む若年層との接点を増やすことに注力している。
また、部門横断的なタスクフォースによる新製品開発にも力を入れており、マーケティング、デザイン、製造の垣根を越えて共同でプロジェクトを遂行。例えば「サマー・シャンパン」や「ヘネシー・バイ・ケンゾー」などの製品は、まさにその成果といえる。



部署の壁を超えてアイデアを形に…なんかワクワクしますね!
人材面でも、海外経験を通じてグローバルマインドを育てる方針が定着し、若手には最低1度は外国勤務の機会を与える方針。まさに「世界を見て、世界で戦う」人材づくりを実践している。
さいごに
LVMHの成長を支えたのは、買収によるスピード感ある拡大戦略と、それに矛盾しないよう絶妙に設計された分権型のマネジメント、そして人材への継続的な投資である。ブランドごとの独自性を守りながら、グループ全体で成果を出すというこの両立は、まさに芸術の域に達している。
ビジネスの現場で参考になるのは、「理念と仕組みを両立させる力」部分で、私自身の実務にも応用できそうな学びが多く、まさに記憶に留めておきたい一例となりました。







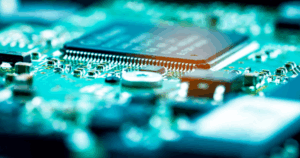


コメント