こんにちは、Yatzです!
「ビルの未来を変える。」これは一見すると大げさに聞こえるかもしれませんが、ジョンソンコントロールズ株式会社(以下、JCJPN)の事業に触れると、その言葉が決して誇張でないことに気づきます。
今回学んだケースでは、建設業界において専門性の高いビルオートメーションという領域に挑み続けるJCJPNが直面している課題や、その背景にある業界構造、さらには人材戦略や働き方改革について、自分なりの備忘録としてまとめました。あくまで現場視点での気づきをベースに、「働きがい」や「持続的成長」のヒントを探る内容となっています。
(シバキチ顧問)「ふむふむ、まじめなテーマだが、肩肘張らず読んでいこうじゃないか」
ケース要約
JCJPNは、グローバルで約10万人の従業員を抱えるジョンソンコントロールズ・インターナショナル(JCI)の日本法人で、1971年の設立以来、空調やビルオートメーションシステムの設計・施工・保守を主力事業として展開しています。日本全国に約40拠点を持ち、従業員数は約1,400人。その約8割が技術系で、現場の最前線で作業に従事しています。
JCIは元々、自動車部品とビル設備のコングロマリットでしたが、2016年以降はビルソリューションに事業を集中。現在はスマートビルやスマートシティを支えるOpenBlueというデジタルソリューションを核に、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するテクノロジーカンパニーへと変貌しています。
一方、JCJPNは日本の建設業界の商流の中で、ゼネコンやサブコンの下に入る専門工事業者としての立ち位置にあり、業界特有の3K(きつい・汚い・危険)や重層下請け構造、高齢化といった慢性的課題に直面しています。
社内では技術職、特にPM(プロジェクトマネジャー)の人材不足が深刻で、若手の定着率の低さや中堅社員の離職などが経営課題となっています。PMの独り立ちには最低でも2〜3年、メガプロジェクトを任せられるようになるには10年以上の経験が必要とされる一方で、労働時間の長さや業務負荷、精神的ストレスの大きさが若手離職の要因となっている実態があります。
これに対しJCJPNでは、業務の標準化やRPA導入、技術者のスキル認定制度、若手のアイデア提案制度「Out of Box」など、多方面からの改善施策を講じてきました。また、50周年を機に社内外へのメッセージ発信を強化し、ブランディングや従業員エンゲージメントの向上にも取り組んでいます。
業界構造の壁と変革の必要性
建設業界の慢性的課題と3Kの現実
日本の建設業界は長年、深刻な人手不足に悩まされてきました。東日本大震災の復興需要、都市再開発、大阪万博やリニア新幹線など、大型プロジェクトが続く一方で、労働集約型であるがゆえに3K(きつい・汚い・危険)のイメージがつきまとうのが実情です。
実際、建設業の年間総実労働時間は2,018時間(2019年時点)で、全産業平均より約20%も長い。また完全週休2日制導入率は27%にとどまり、有給取得率も43.3%と、いずれも全産業平均を下回っています。
さらに現場労働はテレワークができない業種であるため、コロナ禍でも出勤が必要だったこと、そして55歳以上が3割を超えるという深刻な高齢化もあり、若手にとって魅力的な職場とは言い難い現状です。
 ゴリ係長
ゴリ係長この業界、ガテンだけじゃ回らん時代が来てるんだよ。変わんなきゃ、未来がないぜ
ビルオートメーションの現在地と業界特性
ビルオートメーション(自動制御)システムは、空調・防災・電気・衛生などの設備を中央監視し、最適に制御する仕組みで、ビルの省エネと快適性の両立に欠かせない存在です。これらのシステムは、建物の用途や規模ごとにカスタマイズされるため、設計から施工、保守まで一貫した知識と技術が求められます。
国内市場では、アズビルとJCJPNの2社が、システム設計から施工能力まで備えたプレイヤーとして存在しており、非常に競争が少ないニッチな市場です。海外勢の参入障壁が高いのは、単なるソフトウェア開発ではなく、現場施工能力まで含めた総合力が問われるからです。
ただし、JCJPNはゼネコン・サブコンの下に位置づけられることが多く、業界内での発言力が低くなりがちです。この構造が、社内でも長年「卑屈な立場」として捉えられ、社員のモチベーションにも影を落としてきました。
JCJPNの課題とこれまでの対応策
人材確保とリテンションの難しさ
PM職の育成には長い年月がかかる一方で、若手の定着率は年々低下。特にZ世代は「環境貢献」など社会的意義に関心を示す一方で、ライフ重視・短期志向の傾向が強く、入社3年以内の離職率は70%にまで低下しています。
また、業務範囲の広さ、複数現場の掛け持ち、原価管理まで求められる重責、加えて施工現場における地位の低さが精神的なストレス要因にもなっています。
中堅の退職も増えており、採用しても育つ前に辞めてしまうという「育成の空洞化」が起きているのが現状です。
業務改善への多面的アプローチ
JCJPNではこの問題に対し、多角的な対策を講じています。
- RPAやアウトソース導入による業務効率化
- 技術スキルの段階認定制度と報酬の連動(グランドマスター制度など)
- 若手の声を汲み取る「Out of Box」制度
- ナレッジシェアシステム「AskNow!」の構築
- 4週8休の徹底、家族向け感謝イベントの開催
- ダイバーシティ推進とBRG支援



ぼくもOut of Boxに出てみたいです!若手の声って、ちゃんと届くんですねっ
持続的成長に向けた働き方改革の再設計
労務管理から見たPMの働きがいと限界
OHI(組織健康度)調査では、入社3〜10年目、特にPM職のモチベーション・方向性・社風の評価が低い傾向が顕著です。これは、会社の戦略や将来ビジョンが自身の行動に結びついていないと感じている証左と言えます。
また、残業前提の報酬構造や、現場・社内における地位の低さ、裁量と責任のアンバランスが、「やりがい」と「疲弊」の両面でPMの心身に負荷をかけています。
キャリア設計と職場文化の進化
一方で、PM経験者や離職者へのヒアリングからは、仕事への誇りや達成感も強く感じられました。だからこそ、キャリアの見通しを持たせる仕組みや、頑張りが正当に評価される制度が必要です。
また、世代間での価値観のギャップを埋める中間管理職の育成も不可欠。働きがいや報酬、将来像の「見える化」が、職場文化として根付くにはもう一段の工夫とコミュニケーションが求められます。



経験が価値になる職場なら、その経験が継がれる仕組みがいる。それが“文化”ってもんだよ
さいごに
JCJPNが直面している課題は、建設業界という構造的な制約の中で、いかに持続的な成長を実現できるかという壮大なテーマです。
短期的にはPMのリソース確保が急務ですが、長期的には働きがいやキャリアパス、職場文化の再設計によって、より魅力ある企業としての存在感を高めていくことが求められています。
これらの改革が、建設業界全体の進化につながることを願いつつ、今回の備忘録を締めくくります。







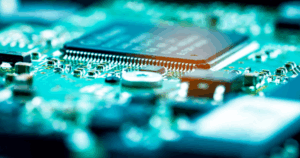


コメント