こんにちは、Yatzです!
富士通は1935年の創業以来、日本を代表するICT企業として高品質や信頼性を重んじる「堅実な企業文化」を背景に、半世紀以上にわたり国内外で多くの実績を築いてきました。しかし21世紀に入り、クラウド、IoT、AIといった新しい技術潮流の中で、従来の「閉じた研究開発」だけでは限界が見えてきました。そこで打ち出されたのが「オープンイノベーション」です。外部パートナーや顧客との共創を通じ、新しい価値を生み出すこの取り組みは、シリコンバレーをはじめとする拠点展開とともに進められました。
とはいえ、富士通のリスク回避体質や縦割り組織文化は容易に変えられるものではなく、過去には協業の失敗も経験しています。しかしその教訓を踏まえ、新しいパラダイムとして「計画型から探索型へ」「ものづくり志向から潜在ニーズ発掘へ」と進化してきました。本記事では、富士通の文化的課題と挑戦、そして「良いことをして成功する」という新しい価値観、さらに東京・サニーベール・サンフランシスコという拠点戦略の意味を整理します。
富士通のオープンイノベーションの歩みと変革の背景
1935年に設立された富士通は、日本初の商用コンピューター「FACOM100」(1952年)を皮切りに、電気通信や電子機器分野で発展し、1980年代には国内外で数々の「初」を実現しました。1990年代にはハードウェアから情報サービスへと軸足を移し、2000年にはクラウドやビッグデータ、セキュリティ分野へと進出。2014年度には売上高が4兆6,000億円、特許は世界で約1万件、子会社420社、従業員16万人を超える規模となりました。
しかし、その成長を支えたのは「品質第一」「リスク回避」を重視する企業文化であり、これが新しい潮流に適応するうえで壁となりました。実際、1990年代にはAppleやAdobeとの協業を模索しましたが、社内の慎重姿勢や外部不信から失敗に終わっています。また2000年代には自然言語処理技術「オントロジー」の外販を試みたものの、法務部門のリスク回避姿勢により市場投入が遅れ、結局は機会を逸しました。
こうした失敗の教訓から、富士通は2010年代に入ると「オープンイノベーション」に舵を切ります。モヒ・アーメッド氏らが中心となり、従来の「計画型・縦割り組織・ものづくり志向」から、「探索型・共創志向・潜在ニーズ発掘」へとパラダイム転換を図りました。その象徴が2015年6月23日にカリフォルニア州サニーベールに開設された「オープン・イノベーション・ゲートウェイ(OIG)」です。OIGは社内外の人材やベンチャーと共に新しい事業モデルを試す場であり、設立から3か月で500人以上が訪問、CNNやニューヨークタイムズ、日経新聞にも取り上げられました。
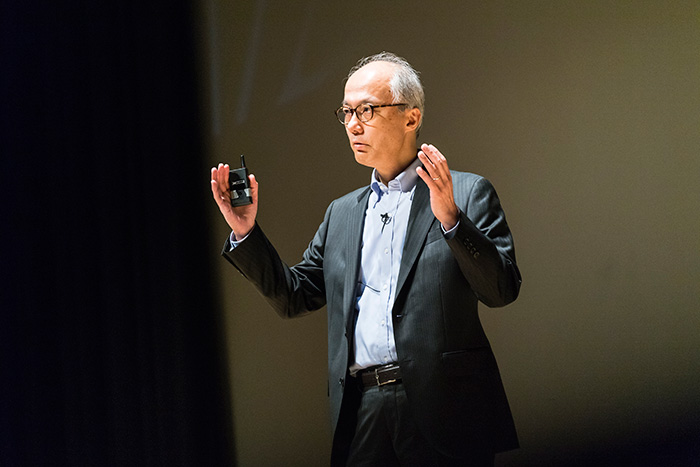
FUJITSUフォーラム:マーケティング戦略本部 VP(当時)高重吉邦 † 出典元:FUJITSU
さらに、サンフランシスコではメイカームーブメントを支援するテックショップとの連携を強化。「Doing well by doing good(良いことをして成功する)」という思想のもと、社会的インパクトとブランド価値を同時に高め、社員に自信を与える取り組みへと発展しました。東京本社を含めた拠点戦略は、社内の文化変革を象徴するものであり、富士通のグローバルブランド構築に向けた挑戦を示しています。
富士通の文化とオープンイノベーションの壁
リスク回避と縦割り体制がもたらす停滞
富士通の企業文化は長年「品質第一」「リスク回避」を重んじるものでした。これは日本の高度成長期においては大きな強みとなり、国内顧客との関係を強固にする役割を果たしました。しかし一方で、不確実性を前提とするシリコンバレー型のスピード経営やリスクテイク文化とは大きな隔たりがありました。加えて、縦割りの組織構造も問題を深刻化させました。研究所が開発した新技術が事業部門に引き継がれず埋もれてしまうケースも多く、外部展開の機会を逃すことが繰り返されており、結果としてせっかくの技術が市場に届かず、変化の早いICT業界で遅れをとることにつながったのです。
 シバ部長
シバ部長守りの文化が強すぎると、攻めの一手を出す前にチャンスを逃してしまうんですよね。
協業失敗から見えた学びと転機
1990年代、富士通はAppleやAdobeとの協業を模索しましたが、外部依存を恐れる経営層の反発で実現には至りませんでした。さらに2000年代には自然言語処理技術「オントロジー」を外販しようとしましたが、法務部門のリスク回避姿勢により交渉が難航し市場投入が遅れ、結果として有望な技術が陳腐化しました。こうした失敗は「自社完結型の開発」や「過度のリスク回避」が、むしろ企業価値を毀損するリスクであることを示しました。この反省が、後のオープンイノベーション推進の原動力となったのです。



法務から分からないダメ出しを良くもらいます。どうすれば良いかを教えて欲しいだけなのに。。。
オープンイノベーションゲートウェイが示す新しいパラダイム
ハードから共創へ ― 顧客との対話による価値創造
富士通は従来、ハードウェア中心の「ものづくり志向」で成長してきました。しかしOIGの設立以降は、製品を売るのではなく「顧客と共に未来を描く」姿勢へと転換しました。顧客が気づいていない潜在的な課題を共に掘り起こし、その解決策を一緒に作り出す。これは単なるサプライヤーから「共創パートナー」への進化を意味します。特にクラウドやIoTを活用したサービス開発は、データを通じた顧客理解を深める契機となり、富士通の新しい強みを築く道を開きました。
縦割りを越えて外部と協業する組織の変革
OIGの大きな特徴は、従来の縦割り構造を超えて、社内外の人材が混ざり合う場を提供した点です。研究所・事業部門・スタートアップが一堂に会し、プロジェクト単位で柔軟に協働する仕組みは、従来の「稟議を重ねて承認を待つ」流れとは対照的でした。さらに、外部のベンチャーや大学研究者との連携を積極的に取り入れたことで、社内では得られないスピード感や多様な視点を獲得することができました。これにより、従来では実現し得なかった試験的なサービスや実証実験が次々と生まれています。



筋トレも会社も“外部刺激”がないと成長しないッス!縦割りを壊すのは筋肉破壊と一緒ッスね!
計画型から探索型へ ― 小さな成功で信頼を積み重ねる
富士通は長年、緻密な計画を立てて段階的に実行する「計画型」の進め方を得意としてきました。しかしOIGでは、予測困難な領域に挑むため「探索型」への転換が進められました。大規模投資を避け、まずは小さな実証を行い、そこで得た成果をもとに経営層や社内を巻き込んでいく。小さな成功の積み重ねが、組織全体に信頼を広げる仕組みとして機能したのです。この考え方は「リーンスタートアップ」に近く、富士通のような大企業がスピードを獲得するための新しい経営モデルと言えます。
「良いことをして成功する」思想の実践
社会的インパクトを軸にブランド価値を高める
「Doing well by doing good」という理念は、富士通のオープンイノベーションに新しい意味を与えました。単に成長分野に参入するのではなく、社会的意義のある取り組みを通じてブランド価値を高める。例えばメイカームーブメント支援では、職人技やものづくり文化の再発見を促すと同時に、グローバルでのブランド認知度を向上させました。これにより、社会課題の解決と企業成長を同時に追求する「二兎を追う」姿勢を打ち出し、企業の存在意義を強調することに成功しました。
社員の自信を育み、スタートアップを惹きつけるビジョン
OIGの活動は、富士通社員に「自分のアイデアが世界に届く」という実感を与えました。これは長年の「下請け型マインド」を打破し、社員の自信と挑戦心を育む効果を生みました。さらに、この変化は外部にも波及します。スタートアップやベンチャーが「富士通と組めば世界に挑戦できる」と感じることで、共創パートナーが自然と集まってきたのです。大企業が示す社会的ビジョンが、外部人材や組織を巻き込む呼び水となることを、富士通は実証したといえるでしょう。



ビジョンがある組織には、人も技術も自然に集まってくるもんだ。理想主義も時に現実を動かす力になる。
拠点戦略とその意義 ― 東京・サニーベール・サンフランシスコの選択
ここでは、授業で、あなたが富士通経営層側に回ったとして、オープンイノベーションの部署が運営する共有スペースはどこに設置すべきだろうかというお題があったのでポイントを記載します。
東京本社 ― 変革の発信地としての可能性と課題
東京本社は、国内の従業員や顧客に対して「変革を本気で進める」という象徴的役割を担います。経営陣が直接関与し、多くの社員が参加することで新しい発想が生まれる土壌を作りました。
ただし、従来の日本的なリスク回避文化や稟議プロセスは根強く、スピード感を持った意思決定には依然として課題があります。そのため、東京本社は変革の「発信地」であると同時に、「最も乗り越えるべき壁」を抱えた拠点ともいえます。
サニーベール ― 協業体験とベンチャー接点の場
サニーベールに設置されたOIGは、既存の富士通拠点を活用しつつ、ベンチャーや大学研究者を巻き込みやすい環境を整えました。シリコンバレーという土地柄、リスクを恐れず試行錯誤を繰り返す文化が根付いており、富士通社員にとっては「協業を体験する学びの場」となりました。一方で、成果を出すスピードや投資対効果の要求は厳しく、従来型の日本企業文化との摩擦も生じやすいという課題もあります。



サニーベール調べたっす。アメリカ合衆国カリフォルニア州にある都市でサンフランシスコ・ベイエリアに含まれるらしいっすね。
サンフランシスコ ― 多様性・ブランド効果と成果主義のリスク
サンフランシスコは世界中の才能とスタートアップが集まる都市であり、ブランド認知度を一気に高めるには最適な拠点でした。メイカームーブメントやテックショップとの連携は、富士通を「ものづくりの再発見」に導くと同時に、社会貢献と事業成長の両立を実感させるものでした。しかし同時に、競争の激しい市場で成果が出なければ存在感を失うリスクも大きく、常にスピードと成果を問われる場でもあります。ブランド向上と結果責任、その両立が課題となる拠点といえるでしょう。
実際はサニーベールに設定。なぜ?
シリコンバレーのエコシステムの活用
スタートアップ、大企業、大学、投資家が密接につながるシリコンバレーは、富士通が目指す「外部と協業するオープンイノベーション」を実践する最適な場所でした。
既存の拠点が利用できた
富士通はすでにサニーベールにキャンパス(元本社ビル)を持っており、その一部を改修することでスピーディにOIGを立ち上げることができました。これはコスト面・スピード面での大きな利点でした。
米国市場とブランド認知
当時、富士通は日本国内では強い存在感がある一方、国際的なブランド認知度に課題を抱えていました。サニーベールはグローバルに注目度の高い場所であり、「世界に向けた変革の発信地」として最適でした。
文化変革がもたらす次の成長への道
富士通のオープンイノベーションは、単なる技術開発の話ではなく「企業文化の変革」の物語でした。
リスク回避や縦割り体制といった日本的大企業の限界を乗り越え、顧客や社会との共創を軸に進化したことは、他の日本企業にとっても示唆に富みます。特に「良いことをして成功する」という姿勢は、社会的課題の解決と企業成長を両立させる新しい道を示しました。
東京・サニーベール・サンフランシスコを結ぶ拠点戦略は、文化変革をグローバルに根付かせる象徴的な取り組みであり、今後の成長に向けた挑戦の基盤となるでしょう。










コメント