こんにちは、Yatzです!
日々の業務に忙殺される医師たちと、その医師に情報を届けたい製薬会社。両者のニーズは高いにもかかわらず、旧来の訪問型の情報提供は限界に達していました。そんな医療業界に、インターネットという武器を携えて現れたのがエムスリー社。今回は、彼らのビジネスモデルと成功の秘密、そして今後の課題について整理しておきたいと思います。
ケースの要約
エムスリー株式会社は、2000年9月にソネットエンタテインメントとの共同事業として設立されました。社名の「エムスリー」は、Medicine(医療)、Media(メディア)、Metamorphosis(変容)の3つの“M”に由来し、インターネットの力で医療のあり方を変革するという理念が込められています。
主力サービスである「m3.com」は、医師を中心とした医療従事者を対象とする日本最大級の会員制医療情報ポータルです。2004年時点では約8万人の医師が登録、2009年3月末には17.4万人の医師を含む44万人の医療従事者が会員となっており、医師総数の約70%に達する規模となっています。
このm3.com上で展開される「MR君」サービスは、製薬会社の本社にいるバーチャルMR(=本社MR)が、インターネット経由で医師に直接医薬品情報を提供する双方向のコミュニケーション・プラットフォームです。医師には「m3ポイント」制度を導入し、情報閲覧に対してポイントを付与。ポイントは書籍などに交換可能で、これが情報受容の動機づけに機能しています。
MR君は従来の訪問型MRと比較してコスト効率に優れており、1ディテール(=1接点)あたりのコストはリアルMRの1万円に対して、MR君ではわずか40分の1、約250円と言われています。しかも、医師の属性に基づく精密なターゲティング配信が可能で、製薬会社の戦略的なプロモーションが実現されています。
2009年時点で26社の製薬会社がMR君を利用し、年間売上のうち約60億円がこのマーケティング支援事業から得られているという実績があります。年間契約金額は1社あたり1.5〜2億円程度で、コンテンツ制作・コンサルティングも含めて一括提供。戦略立案の段階からエムスリーが支援し、薬効ポジショニング、エビデンス設計、サブセグメント選定まで行っています。
さらに、医療従事者向けの求人「m3.com CAREER」や、生活の質向上に関する「QOL君」、医師同士の交流プラットフォーム「Doctors Community」など、周辺サービスも拡充。これによりネットワーク効果が働き、登録医師が増える → サービス価値が高まる → さらに医師が集まる、という好循環が成立しています。
競合としては、ケアネット、メディカルトリビューン、日経メディカルオンラインなどが挙げられますが、エムスリーは「情報の深さと使いやすさ」、「戦略的なコンサルティング力」、「圧倒的な医師会員基盤」で一歩リードしている状況です。
創業以来の試行錯誤の中で、本社MRへの切り替え、eディテールの浸透、そしてコンテンツ主導型の情報発信スタイルへとシフトしたことで、現在の成功基盤が築かれました。
エムスリーが変えた医師と製薬会社の関係
医師にとっての情報収集は、「必要なときに、必要な情報を、信頼できる形で手に入れる」ことが理想です。しかし現実は、製薬会社のMRが病院を訪問し、限られた時間で製品情報を届けるスタイル。内容もピンポイントではないことが多く、時間を奪われる医師にとってストレスになっていました。製薬会社もまた、膨大なMR人件費をかけながらも効率的な情報提供が困難という課題を抱えていたのです。
 ネコマタ商事
ネコマタ商事MRの友人に聞きましたが、アピールのために訪問しないといけないけど、ネタも豊富にあるわけではないので、仕事の多くは雑談だそうです。
エムスリーはこの非効率に目をつけ、医師向けの情報提供プラットフォーム「m3.com」を2000年に立ち上げます。
最大の特徴は、医師が“自分の都合の良い時間”に“必要な内容”だけを受け取れる点。さらに、提供する側の製薬会社もターゲティング機能によって、専門分野や過去の閲覧履歴などに基づいた“適切な医師”に情報を届けられる仕組みを作り上げました。



MRも予算を削られた時期と重なるな。医師の取っては接待もしない、情報も薄いMRの訪問は、ただの厄介事になるタイミングでもあったわけだな。
本社MRという新しいコミュニケーション様式
バーチャルMR「MR君」の登場は、エムスリーの最も革新的な取り組みでした。これは現場のMRではなく、製薬会社本社から直接、医師にネット経由で情報を発信する仕組み。毎週配信される動画コンテンツや医療ドラマ、漫画といった“目を引く仕掛け”と、医師が読むことで得られる「m3ポイント」によって、開封率(閲覧率)を高水準に保っています。
リアルMRの1ディテール(=情報提供1回)当たりのコストが約1万円とされるのに対し、MR君ではおよそ40分の1、つまり250円前後。コスト削減だけでなく、コンテンツの閲覧ログやフィードバック分析を通じたマーケティングも可能にしています。2009年時点で26社が導入し、製薬会社1社あたり年間契約額は平均1.5~2億円。医薬品販促に特化したプラットフォームとしての完成度は群を抜いています。
成功の背景にある、三位一体の革新
エムスリーの成功は、以下の3つの要素が有機的に連携していたからこそ成立しました。
1つ目は、「医師基盤の圧倒的な数と質」。2009年時点で日本の医師の約70%に相当する17.4万人がm3.comに登録。数だけでなく、医師一人ひとりの専門性や関心領域を細かく管理し、製薬会社が届けたい層へのピンポイントな情報提供を可能にしました。
2つ目は、「コンテンツの質とユーザビリティへの徹底的なこだわり」。医学的な正確さだけでなく、視覚的なデザイン、導線設計、情報の粒度まで細かく設計されており、「シンプル」「マチュア(成熟)」「とがっている」という3原則を全社員が共有しています。
3つ目が、「戦略コンサルティング型の提供姿勢」。製薬会社に対しては、単なる広告枠提供ではなく、薬のポジショニングや訴求軸の設計支援を含めてアドバイスを実施。マーケティング戦略からコンテンツ制作、分析・レポート提出まで一括で担い、信頼と実績を積み重ねています。



医師と製薬企業それぞれの満足を追求して参加者の増加につなげる、まさにプラットフォームのあるべき姿だな。
ブランドを守るための“質への執着”とリスク
エムスリーのブランディングは徹底しており、営業・人材・デザインすべてにおいて質を重視。人材も高い問題解決力と業界知見を兼ね備えた人のみを厳選。研修体制も強化し、次世代リーダーの育成にも力を入れています。
とはいえ、リスクがないわけではありません。医師への情報が増えすぎれば「開封率」が下がるリスクがあり、m3ポイントの不正利用や法規制への対応も求められます。また、コミュニティ内での誹謗中傷やなりすまし医師の存在がブランドを傷つける可能性も否めません。これらのリスクをいかに抑えながら、今後も“信頼される場”を維持できるかが今後のカギとなります。
さいごに 業界特有のペインポイント把握
エムスリーの事例は、単なるIT化ではなく、「業界の非効率」をテクノロジーと人材戦略で根本から変えた好例です。
特に業界特有の問題点について的確に把握できたからこその着眼点はさすがでした。
そして、医師と製薬会社双方の“使う理由”を丁寧に設計し、関係性の再構築にまで踏み込んだその手法には、他業界にも応用可能な示唆が詰まっていますね。
今後は薬剤師や患者領域、そして海外展開など、さらにスケールする可能性を秘めていると感じました。
業界特有のペインポイントとして自社のドメインでも「MR君的なアプローチ」ができないか、つい考えてしまいました。




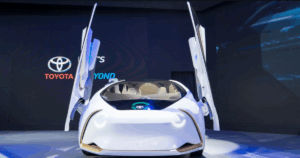



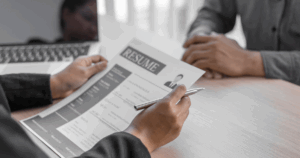

コメント