こんにちは、Yatzです!
かつて高収益企業として名を馳せたローム。
日本の半導体業界が低迷するなか、同社はどのようにして生き残り、そして今、どのような課題に直面しているのか。
ローム浜松を舞台としたケースをもとに、アナログ半導体市場における競争戦略、製造現場のリアル、そして日本企業の生存戦略を掘り下げていきます。
ケース要約
本ケースは、半導体製造子会社であるローム浜松が、1990年代以降の半導体市場の大きな構造変化に対してどのように対応し、現在の戦略的な課題にどう向き合っているのかを描いたものである。
日本の半導体業界は、1980年代には世界シェアの約5割を握る存在だったが、1990年代に入ると、日米半導体協定、円高、バブル崩壊、そしてパーソナルコンピュータ登場による「低価格・短寿命」ニーズの拡大により、一気にシェアを落とした。その中でロームは、主流となった水平分業ではなく、あえて垂直統合型の生産体制を堅持し、素材開発から製造装置までも内製化することで、ローコスト・オペレーションを追求。競合を避けてセットメーカーに“寄り添う”形でニッチ市場を開拓してきた。
2000年代初頭には営業利益率30%を記録し、“勝ち組”と呼ばれたロームだが、2010年代に入ると様相は一変。製品ライフサイクルの短縮や海外勢との競争激化に加え、社内製造装置の性能限界による歩留まり悪化、納期遅延が常態化。平均歩留まりは計画96%に対し実際は94%程度、月平均の機会損失はローム浜松単体で約7億円に上る。また、Appleなど一部顧客は3カ月納品を求めるが、リードタイムは5カ月というギャップがあり、やむなく「先づくり」で対応しているものの、在庫廃棄が月数億円単位で発生している。
人材面でも課題を抱える。長期の新卒採用抑制により中堅層が薄く、近年ようやく人材育成への投資が再開されたが、意識調査では「会社面(方針・制度・体制)」への満足度が低く、上層部のコミットメントの弱さを現場が見限る空気感があるという。
とはいえ、ロームはすでに自動車や産業機器向けのアナログ半導体市場へと軸足を移しており、新しい高付加価値製品群も芽を出し始めている。垂直統合の強みを活かした“つくる力”と、顧客との距離の近さを活かしたR&Dが再び力を発揮できるのか。ローム浜松の未来は、トップの覚悟と現場の本気がどれだけ連動できるかにかかっている。
市場の激変とロームの独自戦略
アナログ半導体とは何か:IoT時代の“縁の下の力持ち”
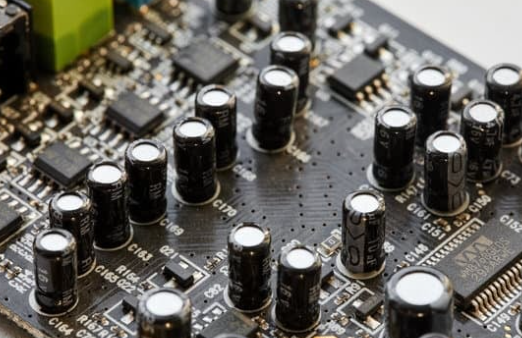
IoTの進展や自動車の電動化といった技術革新が加速するなかで、アナログ半導体の重要性が改めて注目されています。アナログ半導体は、センサやモーターといった“アナログな世界”と、マイコンのようなデジタル機器との間をつなぐ、いわば橋渡しのような存在です。
たとえば温度や光、振動といった物理的な情報を電気信号として読み取り処理可能な形に変換する。地味ながらも欠かせない役割がまさにアナログ半導体となり、ダイオードやトランジスタ、オペアンプ、A/D-D/Aコンバータ、センサーなどいくつか種類があります。
技術の積み重ねが必要な分野であり新規参入が難しく、長年この分野に携わってきた老舗メーカーが上位を占める寡占構造となっています。
垂直統合で「つくる力」を極める
市場の中で、ロームは独自の垂直統合型体制を貫いてきました。
素材開発から、製造装置の設計・内製化、製造拠点のマネジメントに至るまで、全てを自社で一貫して行う体制です。
たとえば、製造装置については、汎用機を購入するのではなく、自社で製作・改良を重ねることで、設備投資を最小限に抑えながら、自社の製品に最適化された製造体制を構築してきました。
この「つくる力」は、コスト削減だけでなく、品質管理やノウハウの蓄積といった面でも非常に大きな武器となっており、まさにロームらしさを象徴する戦略と言えます。
「競合しない」立場で顧客に寄り添う
ロームのもう一つの強みは、セットメーカーと競合しない“部品メーカー”であるという立場です。
たとえば家電メーカーや自動車部品メーカーにとって、ロームは最終製品を持たない中立的なパートナー。だからこそ、製品開発の早い段階から協力関係を築きやすく、情報共有や要件調整もスムーズになります。
さらに、アナログ半導体は1個あたりの単価が非常に安いため、価格交渉にかかる手間(いわゆるトランザクションコスト)をある程度効率化できるロームは、この市場でも利益を確保することが出来ています。
ロームはこうした“外に開かれた”R&D体制を活かし、顧客とともに価値をつくるスタイルを磨いてきた企業だと感じます。
成功からの転換期
高収益からの失速、変わる競争の土俵
2000年前後、ロームは売上3,500億円、営業利益率30%を超える好業績を上げており、業界内でも注目の的でした。
しかし2010年代に入ると、スマートフォンやデジタル家電の短命化や、海外勢との価格競争が激化。ロームの収益力も大きく低下し、利益率は一時10%を切る水準まで落ち込みました。
この局面でロームは事業ポートフォリオの大幅な見直しを進めました。
収益が不安定な民生機器向けから、車載や産業機器といった長寿命かつ価格変動の少ない領域への転換を進めます。こうした市場は信頼性や安定供給が求められるため、ロームの“真面目で堅実なものづくり”が活きる領域と言えるかもしれません。
強豪ひしめくアナログ半導体市場での戦い
一方で、ロームが挑むアナログ半導体市場には、既に強豪が多数存在しています。
Texas InstrumentsやAnalog Devicesなど、業界を代表するプレイヤーは、いずれも高価格・高収益なポジションを確立しており、平均利益率は30〜60%とも言われています。
彼らが扱う製品の中には、1個あたり1,000円以上のものもあり、それに比べてロームの平均単価は20円前後。金額の差以上に、提供できる“価値”の差が問われていることが伝わってきます。
ロームも近年、ハイブリッド車向けの高電圧制御ICなど、付加価値の高い製品を世に出し始めており、今まさに変革の途中にある段階と言えそうです。
仕様書が支配する世界でのジレンマ
この業界では「仕様書」が非常に強力なルールブックです。
価格、品質、納期、全てが仕様書で決まるため、途中変更には対応しにくい。
たとえば、Appleのような大口顧客が3か月後の納品を要求してきたとしても、ローム浜松の製造リードタイムは5か月。どうやって対応するかといえば、“先づくり”で在庫を抱えるしかありません。
ただし、仕様変更やキャンセルが入れば、その在庫は不良資産となってしまいます。実際に、仕掛品の廃棄損失は月あたり約3億円に上るとも言われており、非常に難しい舵取りが求められている状況です。
持続可能なローコスト体制に向けて
受け身の組織文化と「計画通り」の限界
ローム浜松は、親会社からの受注を100%請け負う、いわば“社内ファウンドリ”的な立場にあります。
製品の売価もあらかじめ決まっており、計画通りに作れば利益が出る構造。裏を返せば、イレギュラーな対応には極めて弱いというリスクも抱えています。
ファウンドリ(foundry)
半導体の製造を専門に請け負う企業や工場。例えば、NVIDIAが新しいGPUチップを設計しても、NVIDIAには工場がないため、TSMC(世界最大のファウンドリ)にそのチップの製造を依頼します。
このような“計画主義”は、時として組織を受け身にしてしまいます。
「指示通りにつくる」ことに徹してしまい、コストや納期の改善に対するインセンティブが働きにくいのです。
その結果、多品種少量化に伴う装置の段取り替えや検査工程の負荷が増大し、納期遵守率は悪化。販売機会の損失は、浜松単体で月7億円超にまで達しています。
「人」の問題は、現場の本音に向き合えるかどうか
そして、現場を根底から支える“人材”にも大きな課題が見えてきます。
長期の採用抑制によって中間層が不足し、ここ数年でようやく育成制度や処遇改善が進み始めたところではありますが、社内の調査では「会社への信頼」や「将来への安心感」といった項目の満足度が軒並み低いという結果が出ています。
言葉だけのコミットメントでは、エンゲージメントは高まりません。
トップが本気で変えようとしているかどうか、その“温度感”こそが、現場を動かす唯一のエネルギーなのかもしれません。
さいごに “本気”が伝播する組織へ
ローム浜松が抱える課題は、多くの日本型子会社にも同じことが言えるかもしれないです。
多品種少量、短納期要求、廃棄リスク、そしてモチベーション管理となかなか一筋いかない状況ですね。
それでも生き残るには、親会社が健全なうちにあえてリスクを取るしかない。
市場探査・人材育成・設備投資……子会社に未来への打ち手を任せるには、トップの本気の「コミットメント」が不可欠である。現場はそれを敏感に感じ取り、「本気で応える」ことでしか報いることができない。
「上司が本気かどうか、部下は簡単に見限る」これはあらゆる組織の普遍的な真理だ。
変化の時代を迎えたアナログ半導体業界。日本のものづくりが再び脚光を浴びる日は、トップと現場が“本気”でつながったときに訪れるのかもしれない。

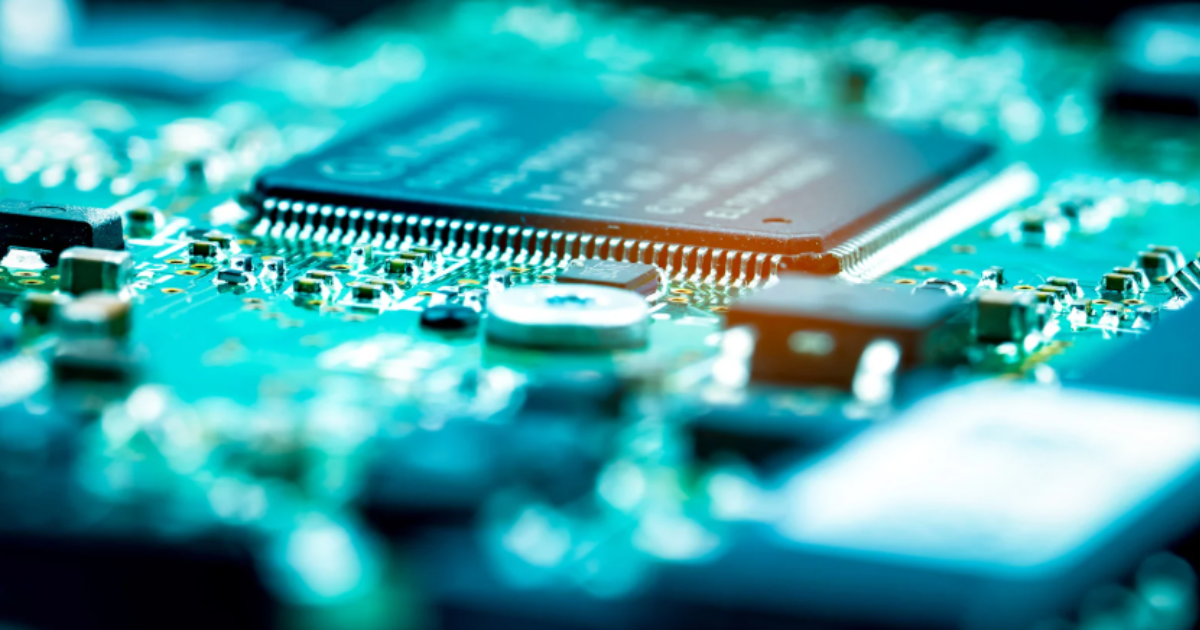








コメント