こんにちは!Yatzです。
名古屋商科大学MBA授業の備忘シリーズとして今回はStrategic Thinking(戦略的思考)の授業について記載します。
この授業は、戦略と論理的思考の基礎を学ぶことを目的としたもので、MBAコースの導入として位置づけられています。「戦略とは何か?」という本質的な問いに向き合いながら、実際の企業事例を通して「考えて伝える力」を磨いていく構成でした。
で結局【Strategic Thinking】なんやねんですが、ざっくり言うと「戦略的に考え、論理的に伝える技術を身に付ける」ための実践型授業ということですね。
受講した感想としては、企業の成功・失敗事例をケースで深堀しながら、「なぜこの戦略だったのか?」「別の選択肢はあったのか?」と自分の頭で考え抜く訓練になりました。Nintendo、Walmart、コカ・コーラ、Amazonなど実在の有名企業の戦略を分析する中で、理論よりも「現実でどう活用するか」に重きが置かれていたのが印象的でした。
分析フレームワーク(PEST、5 Forces、バリューチェーンなど)も学びましたが、それらをツールとして使いこなすというより、「何を考え、どう判断するか」という戦略的思考体力を鍛える内容でした。
授業情報
授業の目的
本授業では、戦略的思考と論理的思考の基礎を学びます。特に、MBAで求められる思考法として「戦略=競争に勝つこと」を出発点に、市場・競合・自社の分析とそれに基づく戦略立案の実践力を養成します。ケーススタディを通じて、実践的かつリアルな議論を重視し、「戦術」ではなく「戦略」の視点から思考する力を育てることが主目的です。
担当講師(当時)
この授業の講師は長沢 雄次(ながさわ ゆうじ)先生でした。
略歴
東京大学工学部を卒業後、ハーバードMBAを取得。日商岩井、ソフトバンク、PwCなどを経て、自ら起業も経験。現在はNUCB教授。
吹き出しコメント案
コンサル、ベンチャー、ITと幅広いキャリアを経ておられる先生で、特に「現場感のある戦略」の話が多く、納得感がありました。
取扱いケース
- パワープレイ(A): 任天堂と8ビット・ビデオゲーム
- パワープレイ(B)(C): セガと16ビット・ビデオゲーム/3DOと32ビット・ビデオゲーム
- ウォルマート・ストアーズ
- ヨーロッパをめぐる熾烈な争い:ライアンエア(A)(B)
- ヨーロッパをめぐる熾烈な争い:ライアンエア(C)
- コカ・コーラ対ペプシコーラと清涼飲料業界
- オンラインの覇者(A):バーンズ・アンド・ノーブル対アマゾン
- 日本トイザらス
授業を受けた感想(ダイジェスト版)
学びの備忘メモ
の授業で印象的だったのは、戦略フレームワークの正確な理解と使い分けが強調されていた点です。たとえばPEST分析では、政治・経済・社会・技術の観点を通じて「企業が制御できない外部環境」を整理し、業界構造の変化を読むことが求められました。また、5 Forcesでは「業界の魅力度」を多角的に評価し、単なる構造分析にとどまらず、そこから戦略仮説へと発展させる活用が重要視されました。
さらに、バリューチェーン分析では、各活動がどのようにコスト削減や利益拡大に貢献しているかを見える化し、全体の価値連鎖における整合性を評価する姿勢が求められました。ライアンエアやウォルマートの事例では、単一施策の羅列ではなく、「固→変→利→売」の流れの中で戦略の一貫性を理解することが鍵となりました。
この授業で良かった点の感想
フレームワークやマーケティングの知識がないままこの授業に突入した私にとって、最初は正直プレッシャーもありました。しかし、長沢先生のエネルギッシュなファシリテーションと、フレームワークに固執し過ぎない実践的なアプローチに大いに助けられました。
たとえば、単なる分析手法の学習ではなく、「なぜこの戦略だったのか?」「経営者ならどう判断するか?」という問いに向き合うことで、実務と学問の橋渡しができたと感じます。また、どのケースも議論中心で進むため、知識よりも自分の思考と発言が問われる環境に引き込まれ、気づけばあっという間の4日間でした。
戦略思考に対する「怖さ」が「面白さ」へと変わった授業だったと思います。
参考図書
教科書は必ずしも必要ないですが、授業の理解深度的にも、普段のビジネス的にも買って損はない一冊が指定されています。




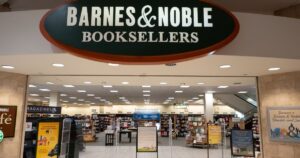






コメント